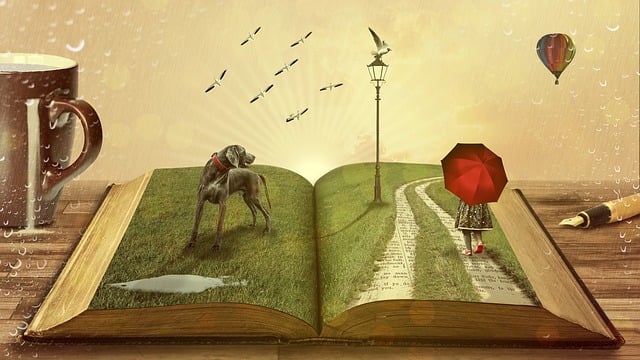皆さん、こんな経験はありませんか? 部下から「あの人の言い方がきつくて…」と相談されたものの、どう対応すればいいのか迷ってしまった。あるいは社内でハラスメント対策委員会を立ち上げたけれど、実際にケースが発生した時に「これって本当にハラスメント?」と判断に悩んだ…。
研修やセミナーを行う中で、こうした悩みを抱える管理職や人事担当者の方々とたくさんお会いしてきました。組織のリーダーとして、部下の声に耳を傾けたいという思いはあるのに、具体的にどう対応すればいいのか、その方法がわからずに困惑されている姿も見てきました。
3月6日と7日の両日で、一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会主催の「ハラスメント相談員養成講座」第4期を担当させていただきました。この講座では、そんな悩みを抱える方々が全国からオンラインで集まりました。コンサルタント、社会保険労務士、企業の相談窓口担当者など、様々な立場の方が参加されています。
特に印象的だったのは、参加者から寄せられる質問の具体性です。
「グレーゾーンのケースでの対応をどうすればいいか」
「過剰に反応する相談者にどう寄り添えばいいか」
「匿名性を確保したいという要望にどう応えるか」…。
これらは教科書には載っていない、現場ならではの切実な悩みばかりです。
ある参加者は「相談を受けたはいいけれど、その後どうフォローすればいいのか悩んでいました」と話してくれました。別の方は「経営者の立場の人が相談窓口になることの是非について意見を聞きたかった」と率直に語ってくれました。
こうした声を聞くたびに思うのは、リーダーシップとは単に指示を出すことではなく、メンバーの声を丁寧に「聴く」ことから始まるということ。しかし、その「聴く」というスキルこそ、実は最も難しいものです。
私たちの講座では、ロールプレイングを通じて実践的に学びます。
相談を受ける側、相談する側の両方を体験することで、「ああ、こういう言い方をされると心が閉じてしまうな」「このような聞き方をされると話しやすいな」という気づきが生まれます。
これまで4回この講座を担当させていただきましたが、ある企業の人事担当者は、講座後に「相談員としての役割の中で、解決策を提示することばかりに気を取られていましたが、まずは相手の話をしっかり受け止めることの大切さに気づきました」と感想を寄せてくれました。
組織の中でハラスメントの問題が表面化しないのは、必ずしも問題がないからではありません。「言っても無駄」「言うとかえって自分が不利になる」という諦めや不安が声を押し殺しているケースも少なくありません。
だからこそ、「あなたの話を聴きます」と言える信頼される窓口の存在が重要なのです。そして、その窓口を担う相談員の育成こそが、組織変革の第一歩になります。
次回の講座は5月に予定しています。
もし皆さんの組織で相談窓口の設置や相談員の育成にお悩みなら、ぜひ参加を検討してみてください。職場の安全を守るという大切な役割を担う相談員の育成を通じて、誰もが安心して働ける環境づくりのお手伝いができれば幸いです。
詳細・お申し込みはこちらからどうぞ
https://harassment-rma.jp/counselor/
皆さんの組織の中に、声なき声に耳を傾ける文化を育てていくこと。
それが、これからの時代に求められるリーダーシップの一つの形なのかもしれませんね。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて
無料相談会を開催しています。
ヒューレット・パッカード社の創業者が残した「人の成長なくして企業の成長はない」というメッセージは、その後リーマンショック等を経て事実上各社で証明され続けている実態があります。こうしたことからも、企業では社員を育成するための様々な研修を企画されていることと思います。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて企業様ごとの個別無料のオンライン相談会を開催させていただいております。お気軽にお問合せ・お申し込みください。
そのほか、自社の研修を新たに導入することに関するご相談をオンラインでお受けしています。
・現状ではどういった研修を導入すると良いのか
・研修はどの頻度で実施すると良いのか
・フォローアップはどのように進めると効果があがりやすいのか
・階層ごとにどういった教育が必要なのか
・自社の教育体系施策を作成したいが、作り方がわからないし現実的かがわからない
など、従業員育成に関するあらゆるご相談を無料でお受けしております。
ご希望の方は、以下のお申し込みフォームからお申し込みください。
追ってご連絡をいたします。
ぜひ、無料個別相談をご利用ください。
組織こうどう研究所