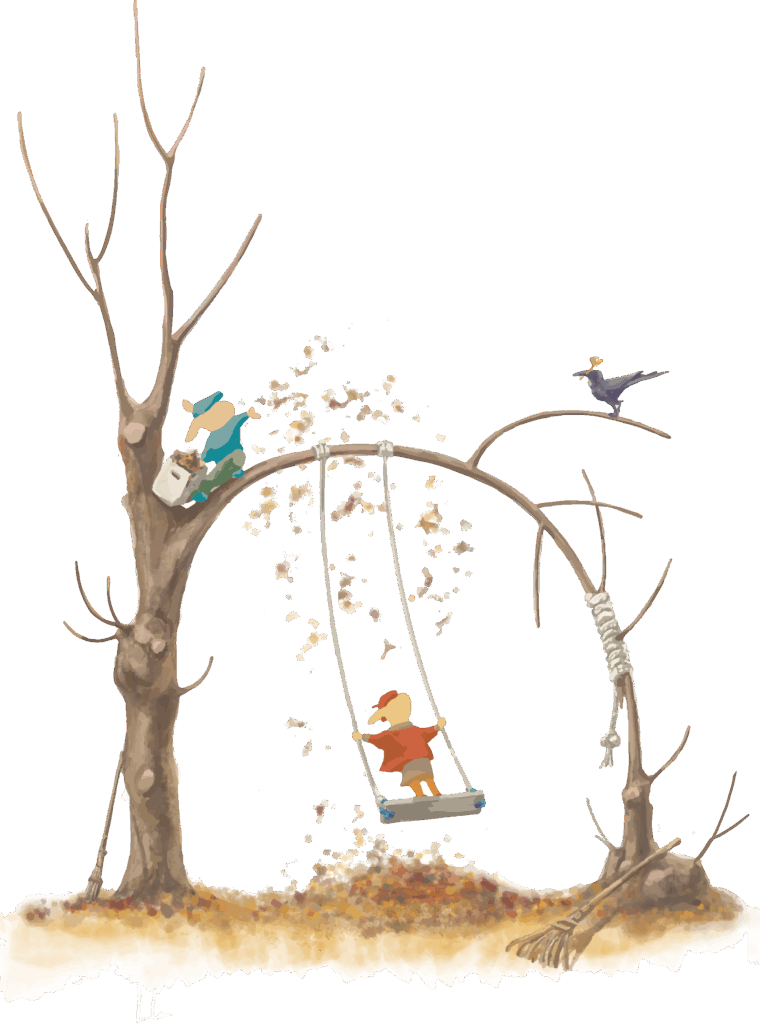人のことは、よく見える
「Aさんって、いつも部下に細かすぎるんだよなぁ」
「Bさんの会議の進め方、ちょっと非効率じゃない?」
こんなふうに、周囲の人の“課題”って、不思議とよく見えるものです。
とくにリーダーやマネージャーといった立場になると、部下の振る舞いやチームの状況に対して「改善すべき点」が自然と目に入ってくるようになります。
私自身も、かつては研修中に受講される方の「発言が少ない」「リアクションが薄い」といったことが気になっていました。でも、ここに私の課題は隠れていたわけです。
「それって本当に“相手の課題”なんだろうか?」と立ち止まってみると・・・
そこには自分の中にも見えていなかった“課題”が潜んでいました。
そのとき、「なぜ自分はそこに着目するのか」の問いを持つ

相手の行動や言動にモヤっとしたとき、少し立ち止まって考えてみる。「なぜ私はここに反応しているのだろう?」と。
これは、私がファシリテーション研修などでよく使う自分への問いでもあります。
ある管理職研修の場面で、受講者の一人が「部下がどうしても指示待ちで、自分で考えようとしないんです」と語ってくれました。その方の悩みは切実でしたが、対話を重ねていくうちに、実はその方自身が「正解を早く出したくて、部下に考える余白を与えていなかった」という構造が見えてきました。
つまり、「部下の指示待ち=相手の課題」と見えていたものが、「自分が余白を与えることに不安を感じていた=自分の課題」だったわけです。
「なぜそれに反応したのか?」の問いには、驚くほど自分の思考パターンや価値観が映し出されます。これは少し怖くもありますが、同時にリーダーとしての成長のチャンスでもあります。
すなわち、自分がコントロールできる対象は、自己課題の方なのですよね。
自分のフレームが見つかったそのとき
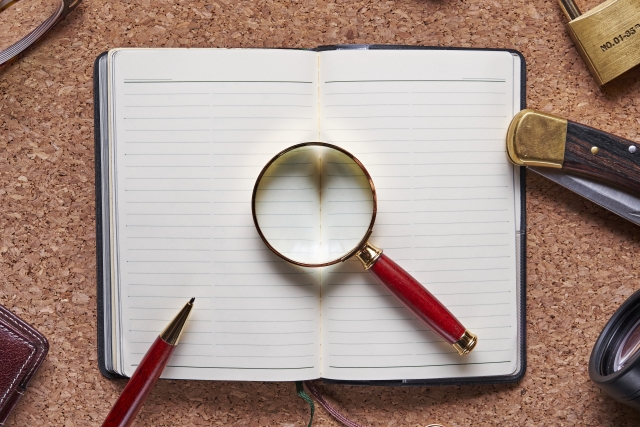
私たちは、無意識のうちに「こうあるべき」「こうすべきだ」という“自分のフレーム(枠組み)”を通して物事を見ています。そして、このフレームがあるからこそ、他人の“課題”が目につくのです。
先ほどの例のように、正解を急ぐ癖や、成果を早く出さなければという焦り、自分の経験が正しいという前提。これらの思い込みに気づいたとき、「ああ、これは“自分の課題”だったんだな」と認めることができるかどうかが大切です。
私自身、研修のファシリテーション中に沈黙が続くと焦ってしまい、「何か話さなきゃ」としゃべり続けてしまうことがあります。でも、それが参加者にとって“考える時間”だったり、“自分のペースで向き合っている証”だったと気づいたとき、自分に「沈黙=悪いもの」というフレームがあることに気づきました。(理解としては、沈黙は相手の考える時間だ、とわかっていたにも関わらず、です)
この“気づき”こそが、グローウィングポイント。
全ては、自分次第

ビジネスの現場では、リーダーが先頭に立って判断し、行動し、組織を導いていく役割が求められます。けれど、相手の課題に目が向いたときこそ、「それって自分の中にもあるのでは?」という問いを持てるかどうかでリーダーシップの質を大きく変えていきます。
もちろん、“自分のせいにする”とか”全てを自分で背負い込むべき”と言っているのではありません。
しかしながら、「他者の行動に対する自分の反応」には、自分自身の無意識のクセが出やすいという視点を持つだけで、コミュニケーションや指導の仕方をぐっと変化させることができます。
心理学では「他者を変えることはできないが、自分の関わり方は変えられる」という趣旨のフレーズをよく耳にします。そうした意味でも、なにごとも“自分次第”なのだと思います。
まずは、日々のやりとりの中で、「なんで今、自分はモヤっとしたんだろう?」と、小さな問いを持ってみること。それが、自己理解を深め、よりよい関係性を築く第一歩になるのではないでしょうか。

当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて
無料相談会を開催しています。
ヒューレット・パッカード社の創業者が残した「人の成長なくして企業の成長はない」というメッセージは、その後リーマンショック等を経て事実上各社で証明され続けている実態があります。こうしたことからも、企業では社員を育成するための様々な研修を企画されていることと思います。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて企業様ごとの個別無料のオンライン相談会を開催させていただいております。お気軽にお問合せ・お申し込みください。
そのほか、自社の研修を新たに導入することに関するご相談をオンラインでお受けしています。
・現状ではどういった研修を導入すると良いのか
・研修はどの頻度で実施すると良いのか
・フォローアップはどのように進めると効果があがりやすいのか
・階層ごとにどういった教育が必要なのか
・自社の教育体系施策を作成したいが、作り方がわからないし現実的かがわからない
など、従業員育成に関するあらゆるご相談を無料でお受けしております。
ご希望の方は、以下のお申し込みフォームからお申し込みください。
追ってご連絡をいたします。
ぜひ、無料個別相談をご利用ください。
組織こうどう研究所