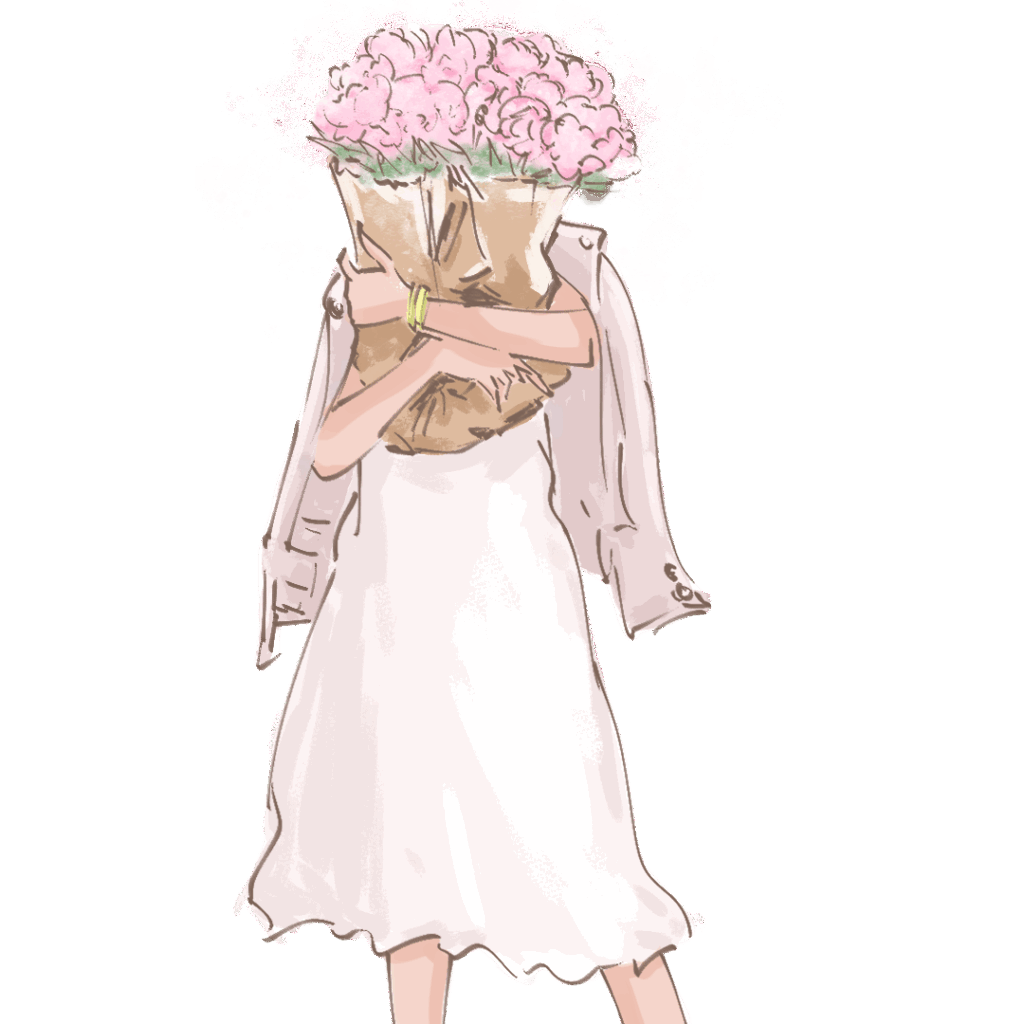言葉に潜む“押しつけ”を手放すという選択
「これは本人のためになると思って言ってるんですけどね…」
職場で、よく聞く言葉のひとつです。
たとえば、部下に資格取得を勧める上司。
「キャリアのために必要だ」と繰り返し伝えるものの、本人はまったくその気がない。
しまいには、声をかけるだけで顔が曇るようになってしまった。
そんなケースに出会ったことはありませんか?
このとき、上司の願いが本当に「悪い」わけではありません。
むしろ、部下の成長を願ってのこと。
でもその“善意”が、「やらされ感」や「押しつけられている感じ」として伝わってしまう。
結果、相手は動かなくなる。あるいは、あえて逆の行動をとる。
人って、不思議ですよね。
心の奥で「その通りかも」と思っていても、「そうしろ」と言われると、なぜかやりたくなくなる。
この現象に名前をつけるとしたら、「選択権の剥奪感」。
“自分で決める自由”が奪われたと感じた瞬間に、人はとても敏感に反応します。
それがどんなに小さなことであっても。
だからこそ、大事にしたい視点があります。
「どうやったら、相手が“自分で決めた”と思える関わりができるか?」
この問いを、自分のポケットに入れておくと、人との関わり方が少し変わってきます。
たとえば…
- 「やってみるとしたら、どこから手をつけたい?」
- 「いまの自分にとって、そのチャレンジってどう感じる?」
- 「もし自由に決めていいなら、どんな方法を選ぶ?」
こんなふうに“相手が考える余地”を残す言葉は、その人の中にある小さなスイッチを探し当てるヒントになります。
質問には、“答えを押しつけない勇気”が宿っています。
そして、“あなたの中にちゃんと答えがある”という信頼も。
そして、
人は、言葉で動かされるよりも、
「あ、これならやってみてもいいかも」と思えたときに、静かに一歩を踏み出します。
その一歩を引き出すために、
伝えるより、問いかけてみる。
背中を押すより、そっと横に並んでみる。
そんな関わり方が、誰かの“やりたくない”を“やってみようかな”に変えるきっかけになるかもしれません。