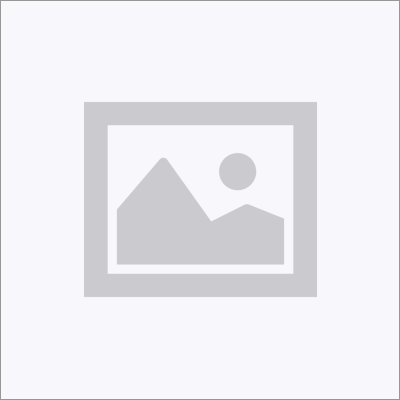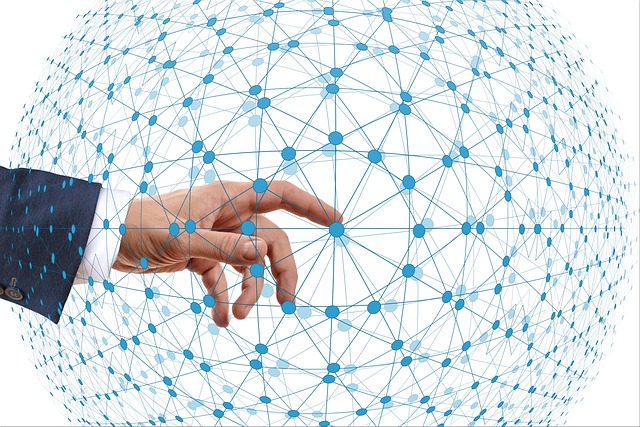「先輩、このボタンを押すとショートカットできますよ」。
若手社員からこんなふうに教えてもらった経験はありませんか?
思わず「なるほど!」と膝を打った瞬間、それはすでにリバースメンタリングが始まっています。
リバースメンタリングとは
リバースメンタリングとは、従来の「ベテランが若手を指導する」というメンタリングの逆をいくアプローチです。若手社員がベテラン社員や管理職にデジタルスキルやトレンド感覚などを教え、組織に新しい風を吹き込む取り組みです。
私が初めてリバースメンタリングという言葉に出会ったのは約10年前。
当時はまだ「そんな逆さまな関係、日本企業で根付くのかしら?」と半信半疑でした。
ところが今や多くの企業が積極的に導入し、組織の活性化に役立てています。
そこには、年齢や役職に関わらず「学び合う関係」を構築することで生まれる豊かな化学反応があるのです。
導入事例

ある大手IT企業では、デジタル・ディバイド(世代間のデジタル格差)を解消するため、30代以下の若手社員と50代以上の管理職をペアリングする取り組みを始めました。月に1回、1時間のセッションで、若手はSNSの活用法やクラウドツールの使い方を教え、管理職はその過程で気づいた組織課題をフィードバックします。
私自身も昨年、ある企業の役員研修でリバースメンタリングを体験する機会がありました。20代の社員から「平澤さんのプレゼン資料、もっとビジュアル重視にした方がいいですよ」とアドバイスされ、目から鱗が落ちる思いでした。
彼らの感覚を取り入れたところ、スライドがすっかり分かりやすくなったのです。
導入した企業が感じたメリットやデメリット
リバースメンタリングのメリットは多岐にわたります。
まず、デジタルスキルや最新トレンドの習得が効率的に進むこと。
若手社員から直接学ぶことで、座学では得られない実践的な知識が身につきます。
また、世代間のコミュニケーションが活性化し、組織の風通しが良くなるという声もよく聞かれます。若手にとっても「自分の知識や視点が会社に貢献できる」という自信につながり、エンゲージメント向上に効果があるようです。
一方で課題もあります。「教える側」になった若手社員の負担増加や、ベテラン社員の中には「教えられる立場」への抵抗感を示す方もいるでしょう。ある企業の人事担当者は「リバースメンタリングを押し付けではなく、自然な学び合いの文化として根付かせるまでに1年以上かかった」と語っていました。
また、取り組みが形骸化してしまい、単なる「若手によるIT講習会」になってしまうケースも少なくありません。相互学習の場として設計し、運営する工夫が必要です。
発想の逆転
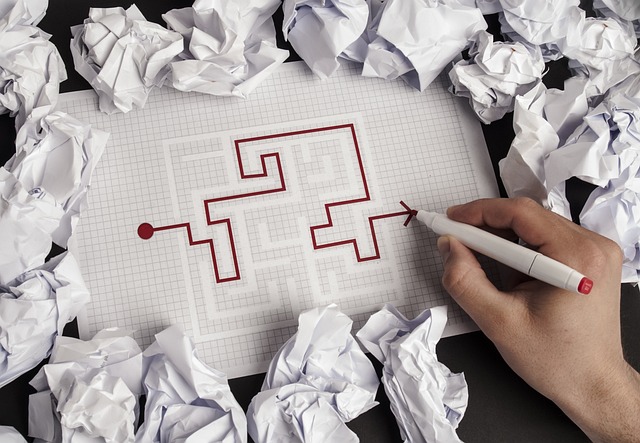
リバースメンタリングの本質は、「教える-教わる」という一方通行の関係を、「学び合う」という双方向の関係に転換することにあります。これは、組織における「知」のあり方を根本から問い直す営みと言えるでしょう。
日本の組織文化では、「年上から学ぶ」「経験者に教わる」という暗黙の了解がありました。
しかし、変化の激しいVUCAの時代においては、経験則だけでは通用しないことが増えています。
年齢や役職に関わらず、それぞれが持つ知恵や視点を大切にする文化へのシフトが求められているのではないでしょうか。
リバースメンタリングは、単なるトレンドではなく、組織の学習能力を高める取り組みです。
「教える」「教わる」という枠組みを超えて、互いの強みを活かし合う関係性が、
これからの組織には不可欠なのだと思います。
もし貴社でも導入を検討されるなら、まずは小さな範囲で試験的に始めてみるのがおすすめです。
形式にこだわらず、「若手の視点から何か一つ学ぶ」という気持ちで臨むことで、
きっと新たな発見があることでしょう。

当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて
無料相談会を開催しています。
ヒューレット・パッカード社の創業者が残した「人の成長なくして企業の成長はない」というメッセージは、その後リーマンショック等を経て事実上各社で証明され続けている実態があります。こうしたことからも、企業では社員を育成するための様々な研修を企画されていることと思います。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて企業様ごとの個別無料のオンライン相談会を開催させていただいております。お気軽にお問合せ・お申し込みください。
そのほか、自社の研修を新たに導入することに関するご相談をオンラインでお受けしています。
・現状ではどういった研修を導入すると良いのか
・研修はどの頻度で実施すると良いのか
・フォローアップはどのように進めると効果があがりやすいのか
・階層ごとにどういった教育が必要なのか
・自社の教育体系施策を作成したいが、作り方がわからないし現実的かがわからない
など、従業員育成に関するあらゆるご相談を無料でお受けしております。
ご希望の方は、以下のお申し込みフォームからお申し込みください。
追ってご連絡をいたします。
ぜひ、無料個別相談をご利用ください。
組織こうどう研究所