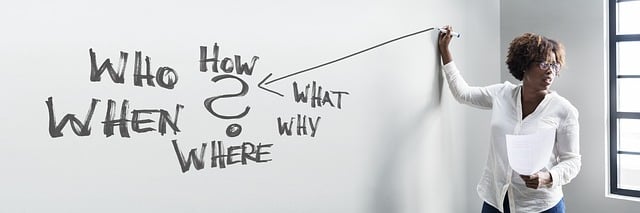「チームワークが大事」とはよく耳にしますが、実際にはどういうことなのでしょうか。
かつて私は(小学校の頃の話ですが)チームは「仲良く、助け合うことがチームワークだ」と思っていました。しかし、意見の食い違いや、互いに遠慮して本音が言えないなど、現実はそんなに甘くありませんでした。あなたも似たような経験はありませんか?
集団の力学を理解する
心理学では、チームの動きは「グループダイナミクス(集団力学)」という視点から分析されます。これは、個人の能力以上に、集団としてどう機能しているかに着目する考え方です。つまり、「チームワークがあるかどうか」とは、集団としてのまとまりや相互作用が健全に働いているかどうか、ということなのです。
ある企業の新規事業立ち上げチームでは、メンバー全員が優秀なのに成果が出ないことがありました。調査してみると、それぞれが自分の専門領域に閉じこもり、情報共有が不十分だったのです。個人の力だけでは、チームとしての力は発揮されないという典型例でした。
T機能とM機能の絶妙なバランス

グループダイナミクスの中核をなすのが、「T機能」と「M機能」という概念です。
T機能は「Task(課題遂行)」、つまり目標達成に向けての行動を指します。対してM機能は「Maintenance(関係維持)」、メンバー間の信頼や心理的安全性を保つ働きです。
以前、私が携わった販促プロジェクトでは、リーダーが非常にT機能に長けた方でした。段取りは明快、進捗管理も抜群でしたが、会議ではメンバーがほとんど発言せず、どこか緊張した雰囲気。結果的に、現場の声が反映されず、プロジェクトは期待通りには進みませんでした。
反対に、あるチームビルディング研修では、和気あいあいとした雰囲気で関係性は良好なものの、なかなか議論が前に進まず、結論が曖昧なまま時間切れになることもありました。これはM機能に偏り過ぎた例と言えるでしょう。
この経験から、「成果を出すこと」と「人を活かすこと」の両立が、チームマネジメントの核心だと実感しました。
機能性が高まると二つの機能は同時に起こる

本当に機能しているチームでは、T機能とM機能が明確に分かれているのではなく、むしろ自然に同時に起こっています。
たとえば、「では、会議を始めます」とリーダーが声をかけた瞬間、私語が止み、皆が議題に集中する。これは一見、T機能=タスクへの集中を促す行為に見えますが、同時に「このチームには共通の合図があり、全員が応える空気がある」というM機能=チームの凝集性や信頼感も働いている瞬間です。
実際、私が関わった新人研修の場面では、毎回冒頭に「最近気づいた小さな成功」を共有する時間を設けていました。すると、自然と場がほぐれ、発言も活発になり、結果として研修内容への集中力も増していったのです。T機能とM機能は、分けて考えるものではなく、互いに作用し合うものなのだと感じました。
明日から実践できるチーム機能の高め方

では、人事担当者として、チームの機能性を高めるために何ができるでしょうか。
1. 会議や研修の「型」を見直してみる
例えば、会議の冒頭5分間で「先週のちょっと嬉しかったこと」を共有する時間を設ける。これはM機能を意識的に取り入れることで、その後のT機能も活性化する工夫です。
2. リーダーの「思考の癖」に気づく機会を作る
「成果を出すことが最優先」と思い込んでいるとT機能に偏りますし、「人間関係を壊したくない」が強すぎるとM機能に偏りがちです。リーダー研修などで、自分のバランス傾向を知る機会を設けてみてはいかがでしょうか。
3. チーム状態を「機能」の視点でチェックする
チームの状態を評価する際、「士気が下がっている」「成果が出ていない」という表面的な症状ではなく、「今、どの機能が不足しているのか」という視点で診断すると、より具体的な改善策が見えてきます。
例えば、ある部署で「報告が遅い」という問題があったとき、単に「もっと早く報告して」と言うのではなく、「報告しにくい雰囲気があるのではないか(M機能の不足)」「報告の基準が明確でないのではないか(T機能の不足)」と機能面から分析することで、本質的な解決につながりました。
チームワークは育てるもの
チームワークは、正解のある「手法」ではなく、日々の中で育てていく「関係性」です。
マニュアル化できる部分もありますが、最終的には「この場にいる人たちと、今、どう関わるか」という日々の選択の積み重ねなのです。
小さな言葉の選び方や、ふとした気配りが、チームの雰囲気を作り、機能性を育てていく。そんな意識からのチームづくりに役立てていただけたら嬉しいです。