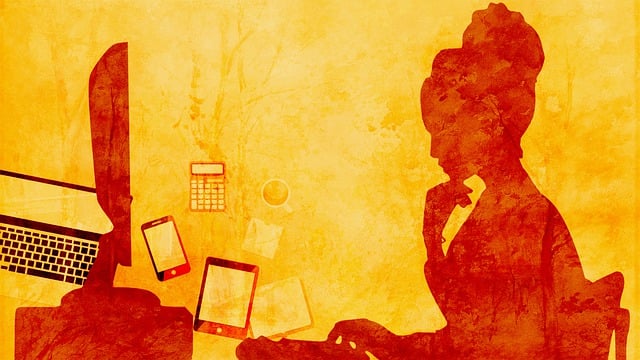メンバーと共に描く目標とプラン――チーム成功への道筋
チームで何かに取り組んでいるのに、ふと「何のためにやっていたんだっけ?」と立ち止まったことはありませんか?
例えば、プロジェクトメンバーそれぞれが忙しく手を動かしているのに、進む方向がばらばら。結果、目標には近づいているはずなのに、どうにも進んでいないような感覚だけが残る・・・というようなこと。
あるプロジェクトでは、目標とプランの明確に価値を置いていました。
その度、より具体的かつ再三にわたって共有行動が行われていました。
「今年度中に不良品率を20%削減する」という目標が掲示され、それに向けた行動を毎日朝のミーティングで実施します。こうした習慣づくりから、メンバーは迷ったときにはメンバー間で相談をしあうようになり、自分の行動を再確認していました。
なぜ「目標共有」がカギになるのか

人間の脳は、明確なゴールがあると自然と行動を最適化する傾向があります。
これは心理学で「プライミング効果」とも呼ばれ、目標が共有されることで、個々の思考と判断に微細な変化が生まれるのです。
ある銀行のCS向上プロジェクトで、私はあえて「この目標の意味」を話し合う対話の場を設けました。当初は「また余計な会議か」という空気も漂っていましたが、徐々に「顧客満足度が上がると、自分たちの働きがいも上がるよね」といった気づきが生まれ、会議後のチームの動きが目に見えて変わりました。
目標の意味を共有しておくことは、困難にぶつかったときの「持ちこたえる力」になります。「なぜこれをやっているのか」の納得感があると、一時の挫折にも折れずに立ち戻れるのです。
プランが見えないと、現場は止まる

目標だけでなく、そこに至るプランも共有されていないと、チームは迷います。
実際にあった例では、プランはリーダーの頭の中だけにあり、その結果、部門間の行き違い、同じ作業の重複、そして予算超過という「もったいない」事態が起きていました。
プランが不透明なままだと、メンバーは毎回「今、何をしたらいいか」をリーダーに聞かざるを得なくなります。これが続くと、まるで自分では判断できないような感覚「学習性無力感」にも陥ってしまうことも。
「会社のビジョンは理解できるけれど、実際に何をすればいいのかがわからない」というケースでは、入社2年以内の離職率が30%を超えていました。不確実な状況に人は強い不安を覚えますが、それを象徴するような現象でした。特にプランが曖昧な状態は、ストレスを招きやすく、組織の安定性にも影響します。
柔軟で見えるチームをつくるには

大切なのは、目標やプランを一度立てて終わりにしないことです。共有しながらも、常に更新していく柔軟性が求められます。
私がご一緒したあるスタートアップでは、毎週月曜の朝に「先週の気づきと今週の焦点」を話す15分ミーティングを続けていました。たった15分ですが、これが組織の微調整の場になり、チームは常に変化に適応しながら前進していました。
また、目標やプランの「見える化」も効果的です。デジタルツールは便利ですが、私はあえて「紙に手書き」でボードに貼ることをお勧めしています。毎日目にすることが、自然と記憶に残るからです。
さらに、目標達成の道のりを「小さな成功体験」に分けておくこともポイントです。
達成感は脳にとってのご褒美。細かく区切って「できた!」を積み重ねることで、チーム全体の活力が高まります。
目標を掲げ、そこに至る道筋をともに描く。それだけでチームは、一体感と方向性を持ち、ぐっと動きやすくなります。
あなたのチームは、いまどんな未来を思い描いていますか?