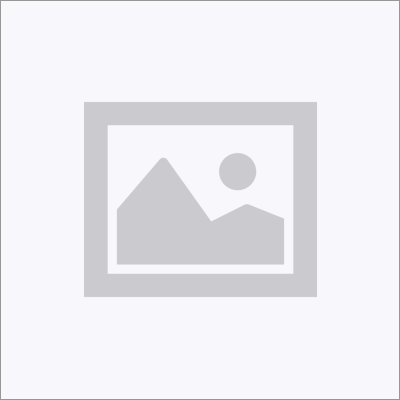「コーチングとは何か ― ティーチングとの違いから考える」
最近、「コーチング」という言葉を耳にする機会が増えました。
上司が部下に対して一方的に指示を出すのではなく、対話を通して自発的な成長を促す。
その考え方は、多くの職場に浸透しつつあります。
けれども、「コーチングって、結局なにをすることなの?」と聞かれると、説明が難しいという声もよく聞きます。そこで今回は、コーチングの基本を改めて整理し、ティーチングとの違いを通してその本質を考えてみましょう。
コーチングとは
コーチングとは、部下が自分の中にある答えを見つけ出すようサポートするコミュニケーションのことです。
コーチは「どうしたらできるのか」「何がうまくいったのか」といった問いかけを通じて、相手の思考を引き出します。大切なのは、助言や指導ではなく、相手の中に眠っている力を引き出すこと。たとえば、「この案件をどう進めたい?」と聞くだけでも、部下は自分の考えを整理し、主体的に動き始めます。
つまり、コーチングの目的は「部下を導くこと」ではなく、「部下自身が自分を導けるようにすること」にあります。
これに対して「ティーチング」は、知識やスキルを伝える方法です。
新人研修でマナーを教えたり、業務手順を説明したりする場面では、ティーチングが必要です。明確な答えがあり、効率的に覚えることが求められる状況では、ティーチングのほうが効果的です。
一方で、部下が「どうすればもっとよい提案ができるだろう」「このチームをどう動かしていこうか」と考えるような場面では、コーチングが力を発揮します。
この二つは対立するものではなく、状況によって使い分けるものです。
ティーチングが「地図を渡す」行為だとしたら、
コーチングは「自分で道を描けるようにする」支援だと言えるでしょう。
コーチングが注目される背景
コーチングが注目される背景には、働く環境の変化があります。
以前のように上司がすべての答えを持っている時代ではなくなりました。
リモートワークや多様な働き方が進み、現場ごとに正解が違う。
だからこそ、上司が答えを教えるよりも、
部下が自分の考えで動けるように支援することが求められています。
たとえば、ある企業では、
会議の進行をリーダーが一方的に決めるのではなく、
メンバーが順番に担当し、コーチングの視点でお互いに質問をし合う仕組みを導入しました。
最初は戸惑いもありましたが、「考える力」と「聴く力」がチーム全体に育ち、
会議の時間が短縮されたそうです。
コーチングの魅力
コーチングの魅力は、部下だけでなく上司自身の成長にもつながる点にあります。
部下に問いかける中で、自分の思考の癖やコミュニケーションの傾向に気づくことがある。
部下の話を聴くことで、「自分もこう考えていたかもしれない」とふりかえる時間が生まれるのです。
つまり、コーチングは「部下育成の手法」であると同時に、
「上司の自己成長のプロセス」でもあります。
部下と上司の関係が、指示と報告ではなく、
学び合い・育ち合いの関係へと変化していく。
これこそがコーチングの最大の意義だと感じます。
コーチングは「人の中にある動きたい力を見つける技術」
コーチングを一言で表すなら、「信じて、待つことの技術」と言えるかもしれません。
急いで答えを出したくなる時こそ、ぐっとこらえて相手の中にある答えを待つ。
上司が「あなたならできる」と信じて見守ることで、部下は自分の力に気づき、動き出します。
もちろん、すべてを任せればいいわけではありません。
必要な知識や手順はティーチングで補いながら、コーチングで自発性を引き出す。
その両輪があってこそ、職場は動き出します。
コーチングとは、「人を動かす技術」というよりも
「人の中にある動きたい力を見つける技術」のように感じています。
次回は「コーチングがもたらす部下育成への効果」について、
もう少し具体的に見ていきたいと思います。