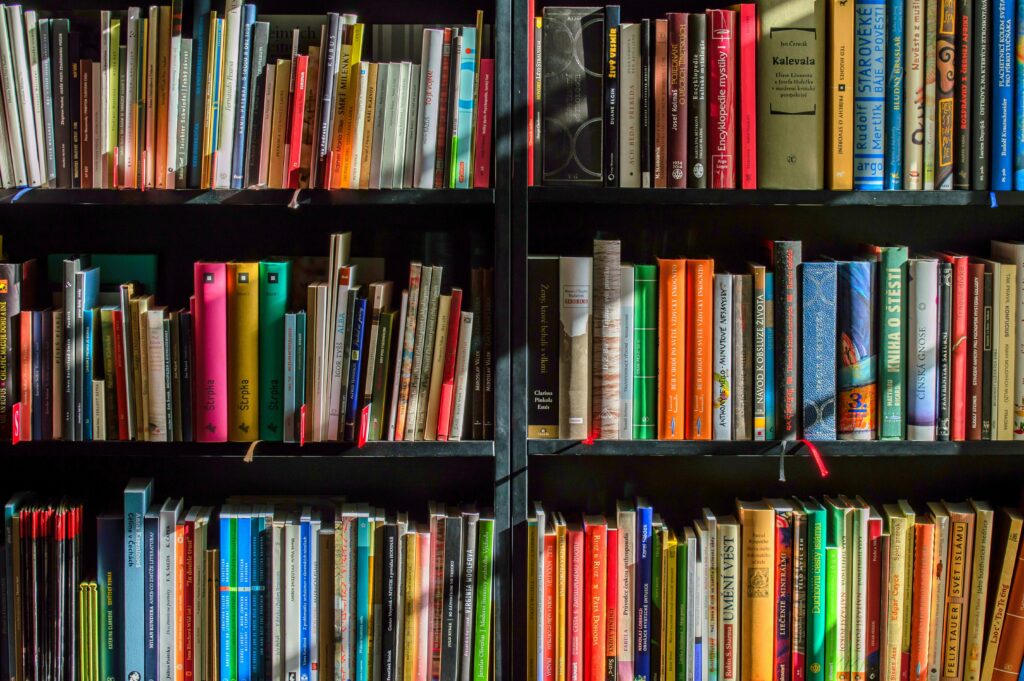コーチングの落とし穴と注意点
コーチングは、相手の力を引き出すすばらしい手法です。
けれども、やり方を間違えると、逆に部下を混乱させたり、信頼を損ねたりしてしまうことがあります。
「せっかく良かれと思ってやったのに、なんだかうまくいかない」
そんなときは、もしかするとコーチングの“落とし穴”にはまっているのかもしれません。
今回は、実際によく見られる注意点をいくつか挙げながら、コーチングをより効果的にするための視点を考えてみましょう。
質問攻め
まず最初の落とし穴は、「質問責め」になってしまうことです。
(実はしたことがあるわたしです・・・😰)
コーチングでは質問が大切ですが、
問いかけばかりが続くと、部下はまるで尋問を受けているような気分になります。
「どう思う?」「それで?」「次は?」と畳みかけると、
考えるよりも“正解を探すモード”に入ってしまうのです。
コーチングの目的は、相手の中にある答えを引き出すこと。
質問はあくまで、その考える時間を支えるための道具です。
たとえば「今、どんなことが気になっている?」と静かに問いかけたあと、
しばらく沈黙を置く。
その“間”にこそ、相手の思考が動き出します。
コーチングは、質問の数ではなく、対話の質で決まるのです。
アドバイスの誘惑
次に気をつけたいのが、「アドバイスの誘惑」です。
経験豊富な上司ほど、相手の話を聞くうちに「こうすればいいのに」と言いたくなります。
もちろん、アドバイスというスキルは有効です。
ただ、今必要か、どのようなアドバイスが必要か、など
診断することが大事です。
いつでもアドバイスをしたくなる。けれども、それをぐっとこらえる。
アドバイスのオンパレードは、部下を一時的に楽にさせますが、
立て続けだと“自分で考える力”が弱まります。
繰り返しですが、「全く助言をしてはいけないわけではありません」。
相手が行き詰まっているときなどは、アドバイスが有効と診断できるでしょう。
「私の経験ではこうだったけれど、あなたはどう思う?」と、
ヒントとして提示する、というのが良いでしょう。
信頼関係を築く前にコーチングを始めてしまう
もうひとつの落とし穴は、「信頼関係を築く前にコーチングを始めてしまう」ことです。
コーチングは“心理的な安全”の上に成り立つ手法です。
相手が「この人は自分の話を否定しない」と思える関係になって初めて、深い対話ができます。
信頼がないまま質問を重ねても、表面的な答えしか返ってきません。
わたしは以前コンサルを受けたことがあるのですが、
信頼関係を築く前から、診断と指導が始まり、
心理的抵抗を抑えるのに苦労した経験があります。
わたしの場合はコンサルティングの場面でしたが、
コーチングでも日頃から「ちゃんと聴いてくれる」「自分を尊重してくれる」
という感覚を持ってもらうことが、前提条件だろうと思います。
信頼関係は、対話のテクニックではなく、日々の態度の積み重ねでしか築けません。
挨拶をする、感謝を伝える、雑談を交わす、
こうした何気ない行動こそ、コーチングの土台を作ります。
成果を急ぎすぎる
また、「成果を急ぎすぎる」ことも注意が必要です。
コーチングの効果は、すぐに数字や行動に表れるものではありません。
部下が考え方を変え、自分の力で動き始めるまでには時間がかかります。
「せっかくやっているのに、何も変わらない」と焦って方向を変えてしまうと、せっかく芽生えた主体性がしぼんでしまいます。
コーチングでは、信じて待つ時間も大事。
その過程を見守る余裕こそ、上司に求められる大切な力です。
誰にでも同じように通用する、のか?
さらに、よくある誤解として「誰にでも同じように通用する」と思ってしまう点があります。
コーチングは万能薬ではありません。
相手の性格や状況によって、効果の出方は異なります。
「どうしたらうまくいくか」を一緒に探る過程そのものがコーチングなのです。
うまくいかないときに、「この人に合う関わり方は何だろう」と
考えてみる。
それは、コーチングを成熟させる第一歩だと思います。
自覚
最後に、コーチングをする上で忘れてはならないのは、
「上司自身も完璧ではない」という自覚です。
上司もまた、学びながら成長していく存在ですから
うまく聴けなかった、いい質問が思い浮かばなかった、という、それ自体も含めて「経験」です。
大切なのは、「次はどう関わろうか」と自分をふりかえる姿勢。
コーチングとは、相手の可能性を信じると同時に、自分の成長も信じる行為なのです。
そう考えると、少し気が楽になりますね。
コーチングは魔法のような方法ではありませんが、
誠実に続けていくと、人と人との関係を確実に変えていきます。
「うまくできなかった」と思う日があっても、あきらめずに対話を続けること。
その積み重ねが、いつか確かな信頼と成長を生み出します。
次回は、コーチングが組織全体にどんな変化をもたらすのか、
未来の展望をお話しします。