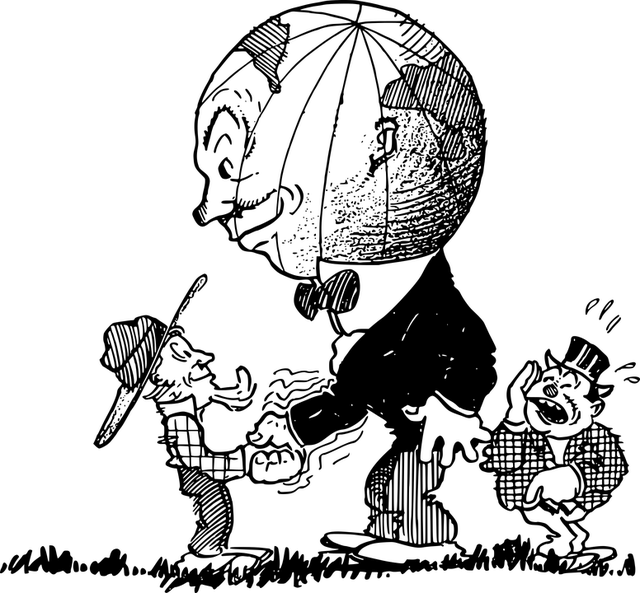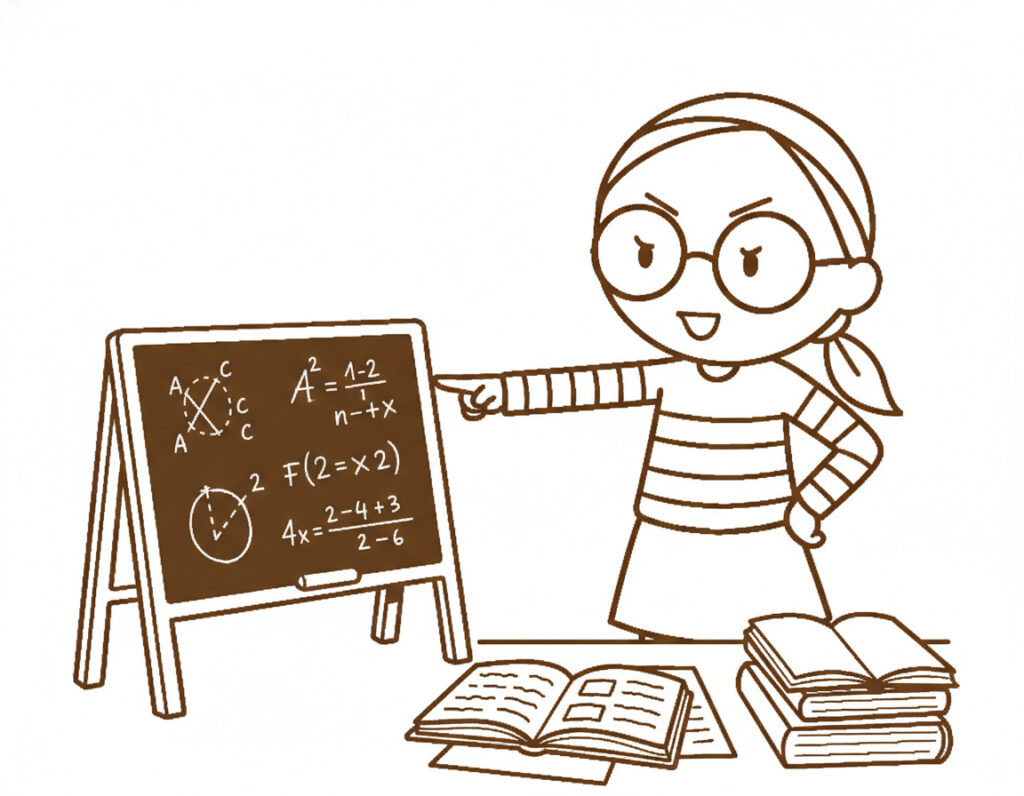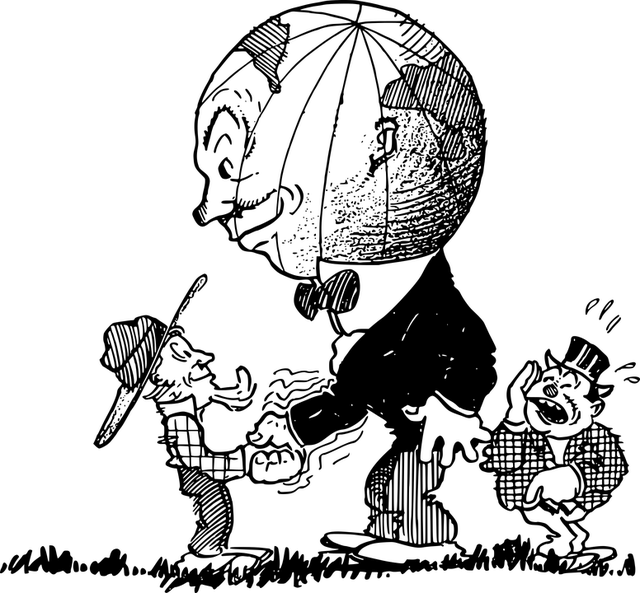
「すごく見せたい」という病
「なぜ、私はあんなに必死に『知っているアピール』をしていたのだろう?」
前回は、25年の経験が「アンラーン(学習棄却)」を阻む足枷になっていた話をしました。
しかし、なぜ足枷になるほど経験にしがみついてしまうのでしょうか。
録画の中の私は、隙あらば専門用語を挟み込んでいました。その姿は、滑稽でした。
そこには自己呈示(Self-presentation)という、人間なら誰もが持つ、しかし取り扱いを間違えると劇薬になる心理メカニズムが働いていたように思えます。
今回は、私が患っていた「すごく見せたい病」の正体と、そこから抜け出すための処方箋について考えます。
私たちは常に「演技」をしている
社会心理学において「自己呈示」とは、「他者に対して特定の印象を与えるために、自分の振る舞いをコントロールすること」を指します。 私たちは日常的に、相手に合わせて「真面目な社員」「優しい親」「頼れる先輩」を演じています。これは社会生活を円滑にするための必要なスキルであり、それ自体は悪いことではありません。
しかし、録画の中の私が演じていたのは、「有能(っぽい)専門家」という役柄だけでした。 周囲に優秀であると印象づけたくて、必死に「理屈」という小道具を使って演技をしていたのです。
(恥ずかしすぎる!)
陥っていた「自己呈示のジレンマ」
ここで、非常に興味深い心理学の概念をご紹介します。
「自己呈示のジレンマ」です。
谷口(2001)の研究などによれば、異性間などの対人関係において、自分の持っている「自己概念(自分はこういう人間だと思っていること)」と、相手が好むであろう振る舞いが対立する場合、人はジレンマに陥ります。
これを私のケース(ワークショップ)に当てはめると、次のようなジレンマが発生していました。
• A:好かれるための自己呈示 素直に教えを請い、場の空気を読む「謙虚な学習者」として振る舞うこと。(=M機能的)
• B:有能さを示すための自己呈示 知識を披露し、鋭い指摘をすることで「優秀な専門家」として振る舞うこと。(=P機能的偏重)
本来、円滑なワークショップのためにはAが良かった、私たち全員にとって、です。
しかし、私はBを選びました。 なぜか? それは私にとって「自分は有能なベテランコーチである」という自己概念が、あまりにも重要すぎたからです。
研究によれば、特定の自己概念の重要性が高いほど、人はそのイメージを守ることに固執し、相手の好みや場の空気を無視してでも、その自己像を押し通そうとする傾向がある、とのこと。 私は「有能さ」を証明したいあまり、「好感」や「調和」を犠牲にするという、最悪の選択をしていたのですね。門等に不毛な活動でした・・・
「有能さ」と「好感」のトレードオフ
悲しいことに、有能さをアピールしようとすればするほど、好感度は下がります。
これを心理学では「有能さと好感のトレードオフ」と呼ぶことがあります。
「私はここまで分かっています」 「この定義は間違っていませんか」
私が繰り出したこれらの言葉は、私の「有能さ」を証明したかもしれませんが、同時に「扱いにくい人」「理屈っぽい人」というレッテルを強固なものにしました。 「すごく見せたい」という欲求は、結果として「ちっぽけな自分」を露呈させるだけの皮肉な結果を招いたのです。
自分でここまであからさまに書けるってことを、成長した、とみなすことにしよう(自己肯定)
矢印を「自分」から「相手」へ
では、この「自己呈示の病」から回復するにはどうすればいいのでしょうか。
それは、自己呈示の「目的」を変えることです。
これは、とっても大事です。
自己呈示の「目的」を変える
これまでの私の目的は、「自分がどう見られるか(自分への矢印)」でした。
これを、「相手に何を提供できるか(相手への矢印)」に切り替えます。
• × 自分が賢く見えるように話す。
• ○ 相手が話しやすいように聞く。
• × 自分の知識を披露する。
• ○ 相手の知見を引き出すための土台になる。
「鎧(プライド)」を脱ぐということは、自分を良く見せるための演技をやめるということです。
やはり、止めるものは、「論理」ではなかったのです!
「自分はすごくなくていい」 そう認めることはわたしにとって怖いことですが、その恐怖を乗り越えた先に、本当の意味での他者とのつながり(M機能)が生まれる、ということを地図のルートに載せることにしました。
自己呈示の呪縛を解く鍵は、やはり「聞くこと」にありそうです。
これまでの「聞く」とは、違う「聞く」ができるようになるかも!!!
次回は、概念論ではなく具体的なスキルとして、M機能(集団維持・配慮)を高めるための「聞く技術」について実践的な話をします。