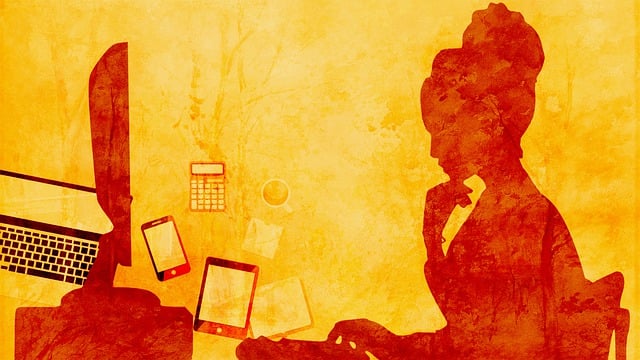
上司の言葉が曖昧だと、部下の行動もあいまいになる
ため息が漏れる会議室

実際に会った話だそうです。
ある企業のマネージャーの方からお聞きした話です。
「何度注意しても直らないんです。何が伝わっていないんでしょうかね…」
このようなお悩みは、決して珍しくありません。
実は私も、昔似たような場面に何度も直面してきました。指導のつもりで伝えた言葉が、部下にとっては「ぼんやりとした印象」でしかなかった、ということが、あとからわかるのです。(伝え方に問題あり!と認識できた貴重な一件でした!)
「しっかりやってね」
「丁寧に確認して」
「ちゃんと、わかるように書いて」
これらの言葉、一見すると優しさもあって良さそうに見えますが、実はとても“曖昧”です。
具体的な行動のイメージが湧かない言葉は、受け取った相手にとって「どう直せばいいか」がわかりづらく、その結果、行動も曖昧になりがちです。
指摘の言葉よりも、”部下の頭の中に「映像」が浮かぶ”説明が必要

私がある研修でお伝えしていることのひとつに、
「言葉を映像化する」という考え方があります。
(ビジュアライズというスキル)
たとえば、「丁寧にやってね」と言うよりも、
「このチェックリストを使って、提出前に一つずつ確認してね」
と伝えるほうが、部下は“何をすれば良いか”が具体的に想像できます。
人は、抽象的な指摘よりも、目に浮かぶような具体的な説明の方が行動に移しやすい傾向があります。
言い換えれば、「丁寧に」という言葉に100人が100通りの解釈をする可能性があるということ。
でも、「A4の資料を2人以上で読み合わせる」といった説明なら、誰が聞いても共通のイメージが湧きやすくなります。
上司として意識したいのは、「この言葉で、相手の頭の中にどんな映像が浮かぶか?」という視点です。言葉を選ぶときに、少しだけこの問いを立ててみるだけでも、ずいぶん伝わり方が変わってきます。
“部下のミス”は、実は“わたしの指導の抽象性”が原因だったと気づいたとき
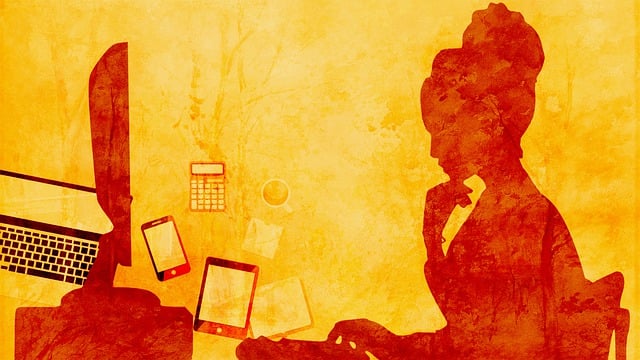
あるとき、報告書のミスが続いた若手社員に対し、「もっと論理的に書いてね」と伝えたのですが、次に出てきたものもやはりピンとこない。何が伝わっていないのか、私自身も少しモヤモヤしていました。
思い切って、「論理的って、どういうことだと思う?」と聞いてみたところ、
「えっと…難しい言葉を使って堅く書くこと…ですか?」と返ってきて、私は思わず苦笑してしまいました。
そうか、「論理的=堅い」になってしまっていたのか…と。
そこで、「この3つの事実を並べるだけで、理由が伝わる構成になってるよ」と、具体的な例を一緒に作って見せたところ、次回から報告書がぐっと改善されたのです。
部下のミスに対して、「どうしてこんな簡単なことが…」と感じるときこそ、上司側が「自分の伝え方は具体的だったか?」と見直すチャンスかもしれません。
具体的に話すこと

まずは「そもそも伝わっていたか?」を振り返ってみるだけで、
指導の質は大きく変わると私は感じています。
部下が同じミスを繰り返すとき、それは“わかっていない”のではなく、
“どうすればいいのかわからない”だけなのかもしれません。
だからこそ、
・「どうしてそれが問題なのか」
・「どう直せばいいのか」
・「直すために何を使えばいいのか」
この3つをワンセットにして伝えることを、意識してみるのはいかがでしょうか。
伝える側の“具体性”が変われば、受け取る側の行動も変わっていきます。
今日は、わたしの小さな体験からのお話でした。








