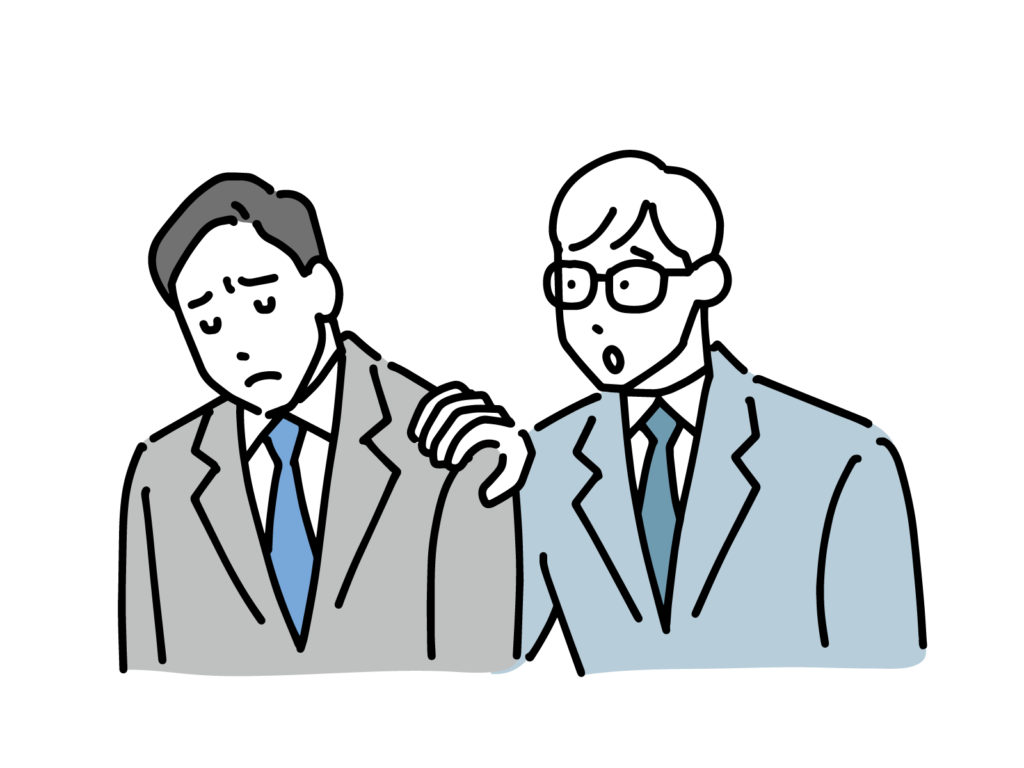“つながりやすさ”が、境界をぼかしてしまうデジタル
〜「公私混同」は、無意識に起きています〜
SNSやチャットツール、オンライン会議・・・
私たちの働く環境は、かつてよりずっと“つながりやすい”世界になりました。
便利である一方で、「つながりすぎている」と感じたことはないでしょうか?
特にリーダーや上司の立場にある方は、職場外でも部下とLINEでつながっていたり、休日にSNSで部下の投稿を目にしたり、あるいはコメントをしたり、という機会が自然と増えているように感じます。
私自身もある時期、研修先のご担当者とFacebookのチャットツールでつながっていたことがありました。何気なく投稿したプライベート旅行の写真に、「次回の資料、いつ届きますか?」とコメントがついた瞬間😰
ふと、線があいまいになっていたことに気づかされました。
公私の境界を曖昧にするのは、強い意図ではなく、“無意識”の積み重ねだと思いました。
デジタルツールの利便性が、「ここまでは仕事、ここからはプライベート」という感覚を、そっと溶かしてしまっていたのです。

「つながっていること」が負担になるときもある
〜言葉ではなく、“ツールの使い方”が圧になる〜
例えば、部下との関係を良好に保つために、気軽なチャットやSNSを使って「声をかける」ことは、決して悪いことではありません。でも、ツールの特性を知らずに使ってしまうと、思わぬ“圧”になることもあります。
あるリーダーが、部下がSNSに投稿した写真に対して「いいね!」を押しただけのつもりでも、部下側は「上司に見られている」「プライベートまで見張られているようで落ち着かない」と感じることがあります。
言葉そのものに問題がなくても、「いつ連絡が来るかわからない」「返信を待たれているかもしれない」と感じること自体が、心理的なプレッシャーにつながることもあります。
ツールは中立です。
けれど、それをどう使うかで、無言の圧力になった事例もありました。
こうしたことから、その視点を持っておくことが、これからのリーダーには欠かせないと私は思っています。
「休日のLINEがプレッシャーだった」部下の本音
「上司から、日曜の夜にLINEが来るんです。『月曜、朝イチでちょっと話せる?』って。内容はたいしたことじゃないのに、休みが終わった気がしてしまいます」たった一通のメッセージが、その人にとっては「休日の終わりを告げる鐘」のように響いていたようです。
もちろん、上司としては「思いついたから送っただけ」「すぐに返してくれなくていいよ」というつもりだったのかもしれません。でも、受け手の状態によりそれをどう受け取るかが変わってきます。
“連絡のしやすさ”と“関係の良さ”は別物です
つながりやすい今の時代、「気軽に連絡できる=良い関係」と思われがちですが、実はそこに罠があります。
良好な関係とは、「必要な距離を保ち合えること」でもあると思います。そう考えると、職場では、つながりすぎて疲弊する関係をつくることではなく、安心して働ける“境界線”をつくることにそのポイントがあるように思えます。
たとえば、LINEではなく業務用チャットにする、時間外のメッセージ送信は翌朝に予約するなど、ツール側でできる工夫もあります。
そして、送る側は、『この連絡、今じゃなきゃいけない?』と一呼吸おいて考えること。これだけでも、部下の週末や心の余白は守られると思います。
便利な時代だからこそ、“つながらない自由”も、大事にしたいですね。