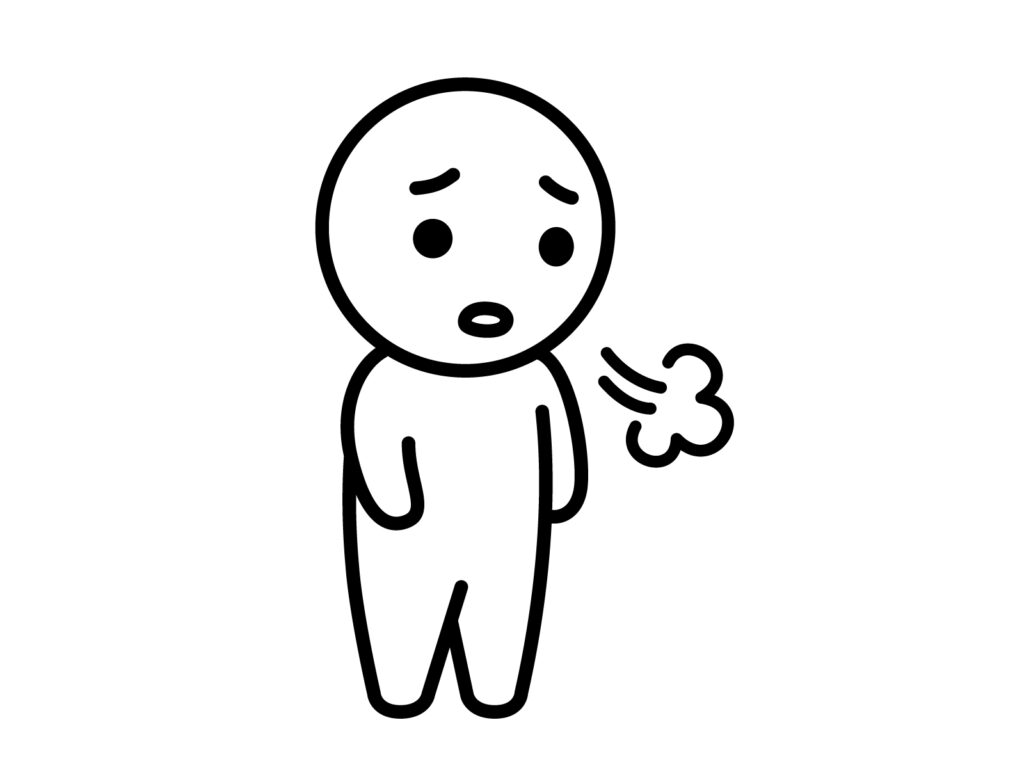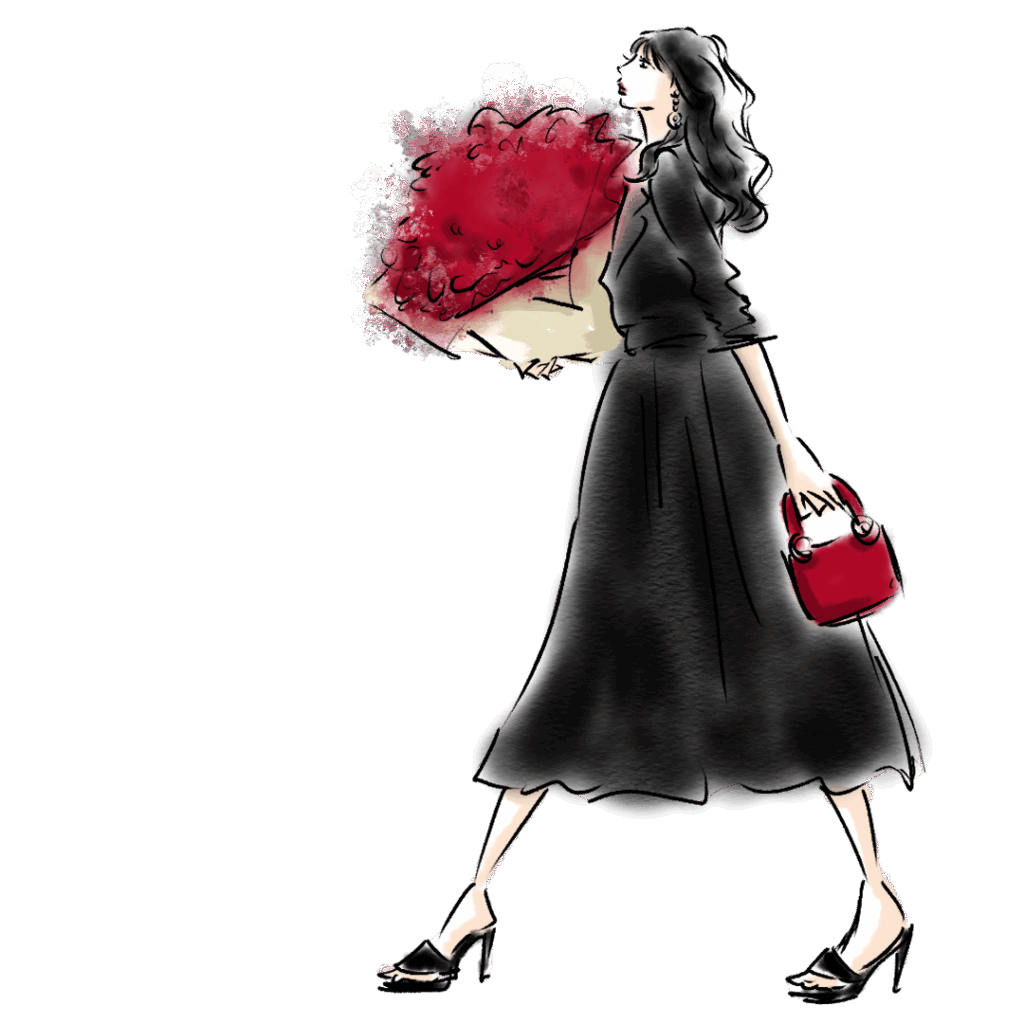〜部下を伸ばすコーチングのポイント〜
コーチングのつもりが、部下を追い詰める“逆効果”になることも
「部下の成長を応援したい」という気持ちから始めたコーチングが、気づけば部下を追い詰めてしまっていた・・・そんな経験はありませんか?
「どうしたらうまくいくと思う?」「次はどんな方法を考えている?」と問いかけているのに、部下の表情はだんだん曇っていく…。
ある管理職の方は、「自分では優しく問いかけていたつもりが、部下から“圧を感じました”と言われた」と話してくれました。意図しない“圧”は、部下にとって「問いに答えられない自分はダメだ」と感じさせてしまうことにつながったりします。
コーチングは本来、部下が自分の可能性に気づき、次の行動を見つけるサポートのはず。でも、やり方を間違えると逆に成長の芽を摘んでしまうことがあるのです。
なぜコーチングがうまく機能しないのか?よくある誤解
では、なぜコーチングがうまくいかないのでしょうか。
よくあるのは「問いかければ相手が勝手に気づいてくれる」と思ってしまう誤解です。
問いかけの質やタイミングが合わないと、相手は“考える”より“答えを探すことに必死”になってしまいます。
例えば、まだ経験が浅い部下に「君はどうしたい?」といきなり投げると、心の中では「そんなの分かるなら苦労しないよ…」と思っているかもしれません。
また、「何が問題だと思う?」という問いも、状況を整理する力がまだ十分でない部下には負担になることがあります。問いかける前に、安心して考えられる土台をつくることが大事なのに、その前段階を飛ばしてしまうケースは少なくありません。
部下が前に進む“問いかけ”と関わり方のポイント
部下が前に進めるコーチングのポイントは、問いの“深さ”よりも“寄り添い方”にあります。
例えば、「どうすればいいと思う?」といきなり聞く代わりに、「ここまでの状況を一緒に整理してみようか」「今できていることは何かな?」と、小さなステップから始めると部下は考えやすくなります。
また、問いかけた後の沈黙を恐れてすぐに補足してしまうと、部下が自分のペースで考える時間を奪ってしまいます。あえて数秒の“待つ時間”をつくるだけでも、部下が自分の言葉で話しやすくなることはよくあります。
そして何より、「答えが正しいかどうか」より、「部下が自分の思考を言葉にできたこと」を大切にする姿勢が必要です。
コーチングは部下と一緒に考えるプロセス――“聴く姿勢”が成果を変える
コーチングは、部下に答えを出させるテクニックではありません。
部下と一緒に考えながら、視点や気づきを広げるプロセスです。
そのために欠かせないのが、“聴く姿勢”です。相手が話している間に「次に何を質問しようか」と考えてしまうと、部下は「ちゃんと聴いてもらえていない」と感じることがあります。逆に、目を見て、頷きながらしっかり聴くだけでも、部下は安心して自分の考えを整理できます。
私自身、コーチングを学び始めた頃は“問いかけること”ばかりに意識が向いていました。でも、実際に一番効果があったのは、ただじっくり聴きながら「そう思ったんだね」と受け止めることでした。
部下が自分のペースで考え、気づき、次の一歩を見つけられるようにする。
そのサポートこそが、コーチングの本質なのだと思います。
部下と話すとき、少しだけ“聴く時間”を増やしてみませんか。
問いかけることより、まずは安心して考えられる空気をつくることから。
それが、部下を伸ばす一番の近道になるかもしれません。
>>ワンポイント<<
例えば、こんな場面はありませんか。
ある管理職のAさんは、成果を出せずに悩んでいる部下に対して、何とか気づきを促そうと「どうしたらうまくいくと思う?」と繰り返し問いかけました。Aさんとしては“考える力を伸ばしたい”という純粋な意図。でも、部下からすると「答えなきゃいけない」というプレッシャーがかかり、かえって思考が止まってしまったのです。
一方で、別の管理職Bさんは、部下が考えやすいようにまず状況を整理し、「いまのやり方でできていることは何かな?」「その中でうまくいったのはどんなところだろう?」と問いかけました。部下は「実はこういうところがネックで…」と自分の言葉で話し始め、Bさんは最後まで否定せずに聴き切りました。結果として、部下自身が「じゃあ次はこうしてみます」と前向きなアイデアを見つけられたのです。
どちらのケースも、問いかけていることには変わりありません。でも、問いかける前の土台づくりや、聴き方の違いが、部下の反応を大きく変えるのです。
まるこの苦い思い出コラム
私にも、コーチングのつもりが“圧”になってしまった苦い思い出があります。
あるとき、新しい業務を任されたばかりの後輩に「自分でどうしたいか考えてみよう」と問いかけました。私は“考える力を育てたい”という思いで、意識的にヒントを与えずに待ったのですが、部下は黙り込み、目が泳ぎ始めました。私は内心「何か答えを出してほしい」と焦り、つい「じゃあ、何が問題だと思う?」とさらに追い打ちをかけるような問いを重ねてしまったのです。
後でその部下が、「あの人、すぐ質問してくるから面倒くさい」「わかんないから聞いてくるのかな?」と言っていると耳に入ってきました。
よほど、ストレスに感じたのでしょう。
面と向かっては「質問に答えられない自分がダメだと思って、どんどん話せなくなりました」と言われました(言っていることが違う、と思いましたが、おそらくどちらも彼女の本音でしょう)。
本当にハッとしました。
問いかける前に、もっと安心して考えられる土台をつくるべきだったと深く反省しました。それ以来、気をつけていることがあります。
問いかける前に関係性を築くプロセスを入れた上で、問いかけなどをする際にはまずは「いまの状況を一緒に整理しない?」とか「できていることから一緒に確認してみよう」と提案してみるようになりました。問いそのものよりも、問いを受け取る人の心の状態が何より大事だと気づいたわたしでした。(苦い思い出ではございましたが😰)