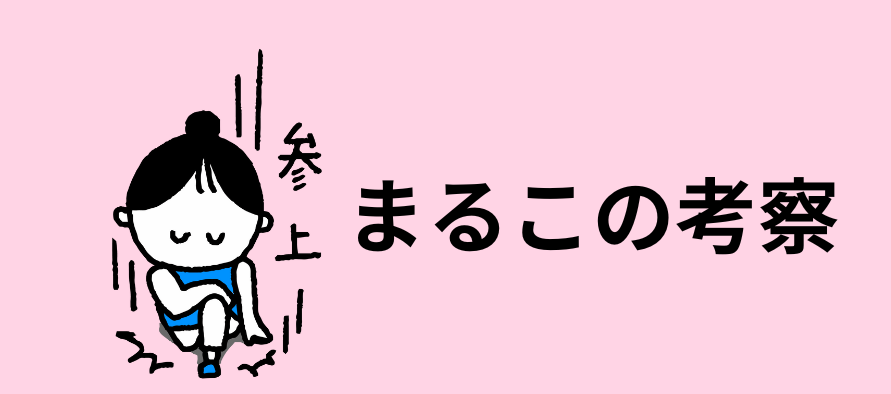こんなこと、ありませんか
プロジェクトの新しいアイデアを思いついたけれど、「でも、失敗したらどうしよう」と思って口にできなかった経験はありませんか?あるいは、部下から革新的な提案を受けたとき、「前例がないから」と却下してしまったことはないでしょうか。
私も提案をする時など、「受け入れられるだろうか」「これまでのやり方から変えて大丈夫だろうか」と不安になることがよくあります。そして気づけば、無難な選択をしていることも…。
失敗を恐れる心理は、私たちのビジネスやキャリアの成長を静かに、そして確実に阻んでいるのかもしれません。
なぜ失敗を恐れるのか

なぜ私たちは失敗を恐れるのでしょうか。心理学的に見ると、これには様々な要因があります。
まず、「損失回避バイアス」という心理傾向があります。
これは、私たちが同じ価値の利益と損失を比較したとき、損失の方を約2倍重く感じる傾向です。
つまり、「100万円を得る喜び」よりも「100万円を失う痛み」の方が心理的インパクトが大きいのです。ビジネスの意思決定でも、成功で得られるものより、失敗で失うものの方が注目されがちです。
また、「社会的評価への恐れ」も大きな要因です。「失敗者」というレッテルを貼られることへの恐怖は、多くの人が抱える不安です。特に日本の企業文化では、失敗が個人の評価に直結しやすい風潮もあります。わたしは、ここがとても強いようです。評価を気にする傾向が強いのですね。
さらに興味深いのは、「完璧主義」の影響です。ある心理学の研究では、完璧主義傾向が強い人ほど、新しいことに挑戦する頻度が低いという結果が出ています。「100%うまくいくことしかしたくない」という思いが、実は成長の機会を奪っているのです。
こんなふうに考えてみよう!

失敗への恐れを克服するために効果的だと思っていることは、「思考の枠組み(フレーム)」を変えることです。
例えば、「失敗」という言葉を「学習機会」と言い換える取り組みです。言葉の力は思った以上に大きく、この小さな変化だけで研修参加者の行動に変化が見られました。
また、「小さく失敗する」という考え方も有効でした。
大きなプロジェクト全体を賭けるのではなく、小規模な試行を重ねていくアプローチです。シリコンバレーの企業で広く採用されている「フェイルファスト(素早く失敗する)」の文化は、失敗のコストを下げ、学びを最大化するための知恵だと聞いています。
私自身も、新しい研修プログラムを開発するとき、まずは信頼関係のあるクライアントに小規模なトライアル(モニター研修)として提案し、フィードバックをもらうようにしています。これにより、大失敗するリスクを減らしながらも、革新を続けることができています。
さらに、「今、何を失うか」ではなく「将来、何を得るか」という時間軸でものを見ることも大切!
目の前の失敗の可能性だけでなく、挑戦しなかった場合の「機会損失」にも目を向けてみましょう。
楽しいが積み重なる毎日に

失敗への恐れを少しずつ手放していくと、仕事の風景が変わり始めます。
聞いたことがある事例を若干の編集を加えてご紹介します。
ある製造業の工場長は、月に一度「挑戦したからこそ起きた、学びの多い機会(事案)」を承認する1to1面談をしました。最初は双方に戸惑いもあったそうですが、次第に職場では仕事をする時の硬さが緩和されてきたそうです。雑談や仕事の相談し合いも増えたそうです。
結果的に、現場からの改善提案が出てくるようになったのだとか。
失敗を恐れずに挑戦できる環境では、仕事が「守り」から「創造」に変わります。
そして何より、毎日の仕事が少しずつ楽しくなっていくのです。(これはわたしの経験則)
最近、私は朝に、夜になったら「今日、いつもと違うことをやってみたとき」「今日、少し冒険してみたとき」をふりかえることができるように、その体験をしようって思ってスタートします。
失敗を恐れるあまり行動を制限するよりも、小さな冒険を日常に取り入れていく方が、結果的に「楽しい」という感情が積み重なっていく小さい経験を積んでいます。
その積み重ねこそ、イノベーションを生み出す土壌になるのではないでしょうか。(いきなり話が大きくなる😰)
こんなふうに、小さな冒険の積み重ねを育んでいけたら、きっと毎日の仕事がより生き生きとしたものになっていくのではないか、そう考えるとちょっとしたドキドキです✨

当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて
無料相談会を開催しています。
ヒューレット・パッカード社の創業者が残した「人の成長なくして企業の成長はない」というメッセージは、その後リーマンショック等を経て事実上各社で証明され続けている実態があります。こうしたことからも、企業では社員を育成するための様々な研修を企画されていることと思います。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて企業様ごとの個別無料のオンライン相談会を開催させていただいております。お気軽にお問合せ・お申し込みください。
そのほか、自社の研修を新たに導入することに関するご相談をオンラインでお受けしています。
・現状ではどういった研修を導入すると良いのか
・研修はどの頻度で実施すると良いのか
・フォローアップはどのように進めると効果があがりやすいのか
・階層ごとにどういった教育が必要なのか
・自社の教育体系施策を作成したいが、作り方がわからないし現実的かがわからない
など、従業員育成に関するあらゆるご相談を無料でお受けしております。
ご希望の方は、以下のお申し込みフォームからお申し込みください。
追ってご連絡をいたします。
ぜひ、無料個別相談をご利用ください。
組織こうどう研究所