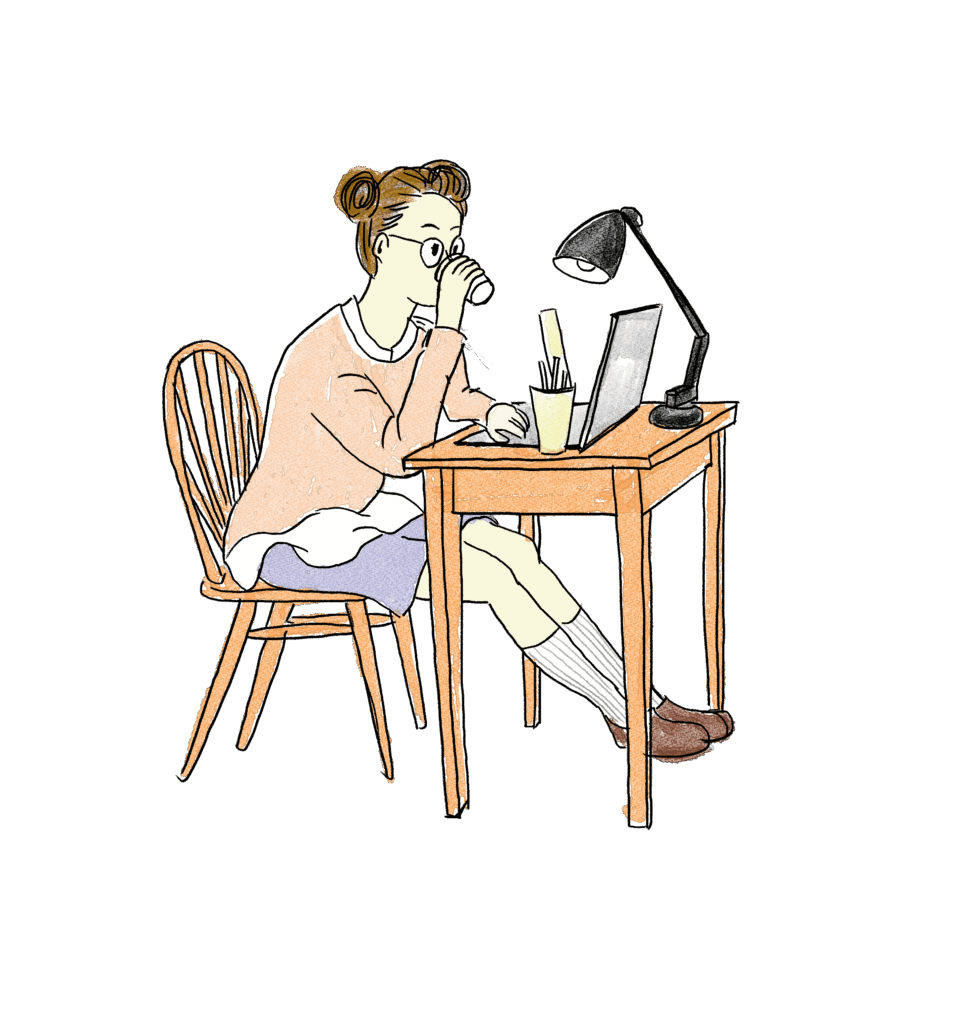「最近、あの人また遅れてるな」
「なんであの部下は、いつも要点がズレてるんだろう」
そんなふうに、他人のことが気になるときって、
実は自分の中にも何かサインが灯っているのかもしれません。
人のことは、よく見えるものです。
良いところも、足りないところも。
「なんでこんなことができないの?」とつい思ってしまう相手がいるときほど、
自分自身の「大切にしている価値観」や「こだわり」が浮き彫りになっている瞬間かもしれません。
例えば、相手にイライラするのは「もっとこうしてほしい」という期待や願いがあるから。
でもそれって、自分の中にある「やり方」や「理想」に沿っている、いえ相手に押し付けているのかもしれません。
そう考えてみると、
私たちは、目の前の相手を通して、
自分の「今」を映し出しているのかもしれません。
またもや話を出して恐縮ですが、
私たちは、自分で変えられること(=影響の輪)しかできないのに、
相手に期待をかけてしまうのですね。。。
【毎度登場】影響の輪と関心の輪
人は、気になること(=関心の輪)に意識を向けがち
しかし、自分で変えられること(=影響の輪)は限られている
スティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』より
自分ができる範囲でしか、人は変われないから
研修でもよく出てくる言葉ですが、「人を変えることはできません」。
できるのは、自分がどう関わるか、どう伝えるかを選びなおすことだけ。
「なぜ言っても伝わらないのか」
「こんなに頑張っているのに、動いてくれないのはなぜか」
と思うとき、そこにあるのは“相手の課題”ではなく“自分の無力感”です。
でも、その感情こそがスタート地点かもしれません。
たとえば、報告が足りない部下がいるとします。
毎回「もっと早く言って」と言っているのに改善されない。
でも、「私の伝え方は一方的じゃなかったか」「そもそも、報告のタイミングや手段を明確にしていなかったのではないか」と、自分がコントロールできるところに目を向けることはできるのです。
人は、自分ができる範囲でしか努力できません。だからこそ、“相手のせい”と思う前に、自分がどう関わっているのかを点検してみることが、変化の一歩になるのだと私は考えています。
「仲間の報連相が足りない」と感じた日の私の反省
あるプロジェクトでチームを組んだときの話ですが、
若手のメンバーがなかなか進捗を共有してくれず、「どうしてもっと報告してくれないの?」と、もやもやしていました。でも、ある日ぽろっと漏らした言葉を、私は聞き逃しませんでした。
「正直、忙しそうで声かけづらかったんです」。
あ・・・私の方だったのか。 と、思いました。
思い返してみると、私は自分のタスクに追われていて、チームの様子を気にする余裕がなかったかもしれません。さらに、過去のプロジェクトでは「なるべく自分で解決してから報告して」と伝えていたこともあり、それが無言のプレッシャーになっていたと気づきました。
つまり、「報連相がない」と私が思っていたのは、相手の怠慢ではなく、私の関わり方の問題でもあったということです。
あの出来事は、まさに“人を見る力”が“自分を見る鏡”になった瞬間でした。
変わるのは“あの人”じゃなくて、“自分”
人を見る力って、本当は「自分を磨く道具」にもなるんだと、思います。
思っていても、なかなか素直にそれを受け入れられない私ですが、
他方で、本当に痛感もしています。
あの人の言動にイラっとしたとき、なぜそう感じるのかを丁寧に考えてみると、自分の価値観や大切にしたいことが見えてきます。それがわかれば、「今、自分が変えることができるのはどこだろう」と少しずつ考えていけるようになります。私の場合、「なぜそう感じるのかを丁寧に考えてみる」ことにとても時間がかかってしまいます。切り替えが遅いのでしょう。すでに学び(気づき)になった時には、ずいぶん経ってしまっていて、機を逸しています。
相手を変えたいというその発想は、幻想
相手を変えることはできません。
でも、自分の関わり方を変えることはできます。
そして、それが結果的に相手に影響を与えることもあるのです。
もし、「あの人、また…」と思うことがあったら、それは「自分の成長のサインかもしれない」と受け止めてみるのも、学習者として最高ランクの見方ではないでしょうか。
私自身、もちろん完璧とは程遠い。そんな中でも、“ふりかえる習慣”があれば、少しずつ変わっていける。こうして、今日も自分の中にある「課題」と向き合っています。
すぐに切り替えられる自分になりたいけど、
なかなか、なんです。わたし。
でも、いつまでも取り組み続けるんだろうなー、って思っています。