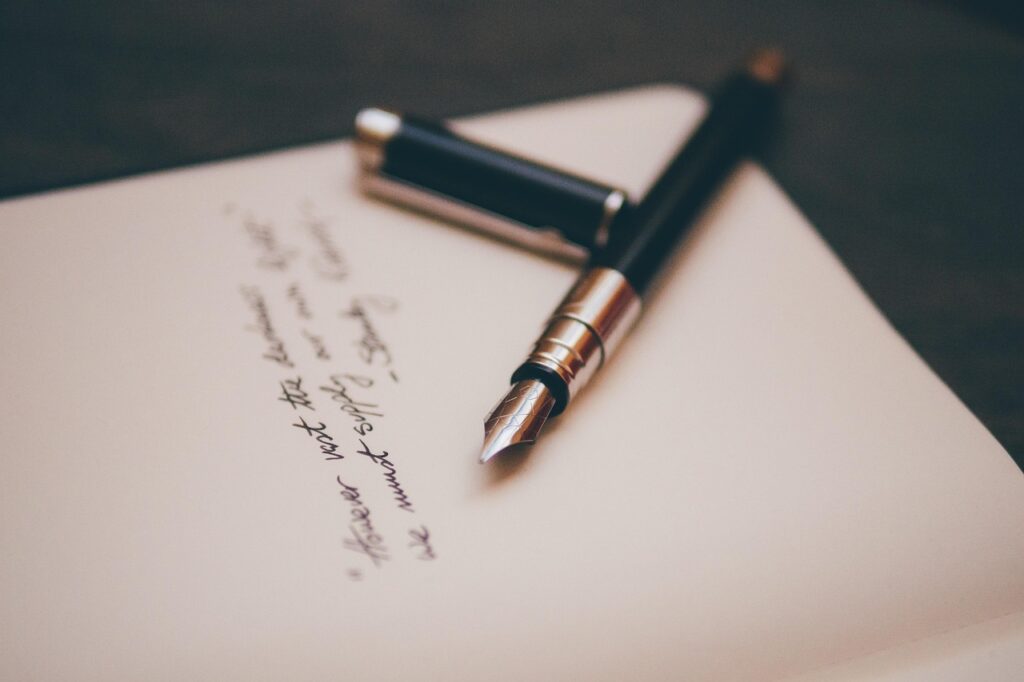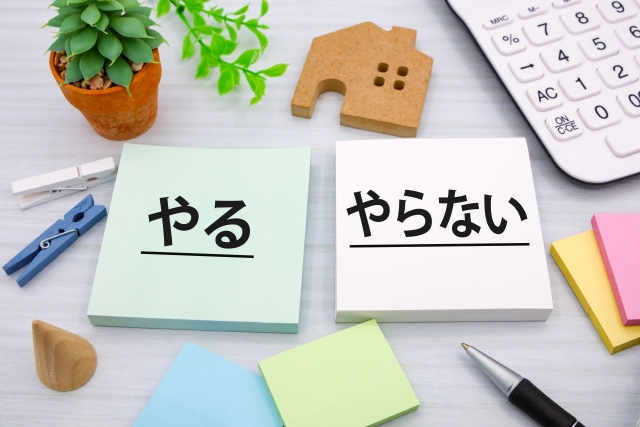「やってみた」だけで変わった日
会議で長々と議論を重ね、「結論は…もっと検討しましょう」で終わってしまう・・・
もちろん話し合いは大事ですが、改善のアイデアは机上の空論だけでは芽が出ません。
一歩踏み出して試してみたときに、はじめて“本当の答え”が見えてくるものです。
私も以前、業務フローの改善案を練りに練った末、「これは完璧!」と思って提案したら…現場の人から「これ、むしろ手間増えてますけど?」と言われたことがあります。
その後、現場の担当者と一緒に小規模テストをしたら、紙よりも数倍スムーズな方法があっさり見つかりました。
現場で起こる“想定外”こそ宝物
改善案を実際に動かすと、想定外のことが次々に起きます。
その中には、「これは困った…」というものもありますが、多くは「おや、こんなに楽になるんだ!」という発見です。つまり、現場で得られる情報は机上では絶対に得られない“生きたデータ”なのです。
たとえば、会議資料のフォーマットをほんの少し変えただけで、作成時間が半分になったケースもあります。これ、議論だけで終わっていたら発見できなかった改善です。
行動のハードルを下げる3つのコツ
- 全部やろうとしない
改善案はまず一部分だけで試すと、結果が見えやすくなります。 - 「失敗」を禁止ワードにする
「失敗」「成功」というより、全ては体験であり、それを積み重ねて経験にしていきます。「失敗」「成功」の定義づけは個人的にはあまりお勧めしません。なぜならば、私たちはそうした言葉にネガティブな感情を持ちがちだし、根拠のない「印象」からの感情から、行動が消極手になったらもったいない、と思うからです。 - やってすぐふりかえる
動いた直後のふりかえりが、次の改善の質を大きく上げます。
前回のコラムでも少し触れましたが、AIやRPAのような新しい技術も、使ってみて初めて本当のメリットと限界がわかります。
「すごいツールらしいから導入!」ではなく、まずは一部業務で試し、その結果を見て判断するのが一番です。
思ったより便利かもしれませんし、「ここはまだ人の感覚が必要だな」という結論になるかもしれません。どちらも自社の状況に合わせて判断ができた、というものです。
論より証拠の業務改善
業務改善は、完璧な計画を立てることよりも、小さく動き出すことのほうが成果に直結します。
動けば現場が教えてくれることが増え、その証拠をもとにさらに良い方法を探せます。
だからこそ、今日からできるのは 「ちょっとやってみる」こと。
あなたの次の改善は、議事録の中ではなく、現場の小さなアクションから始まります。