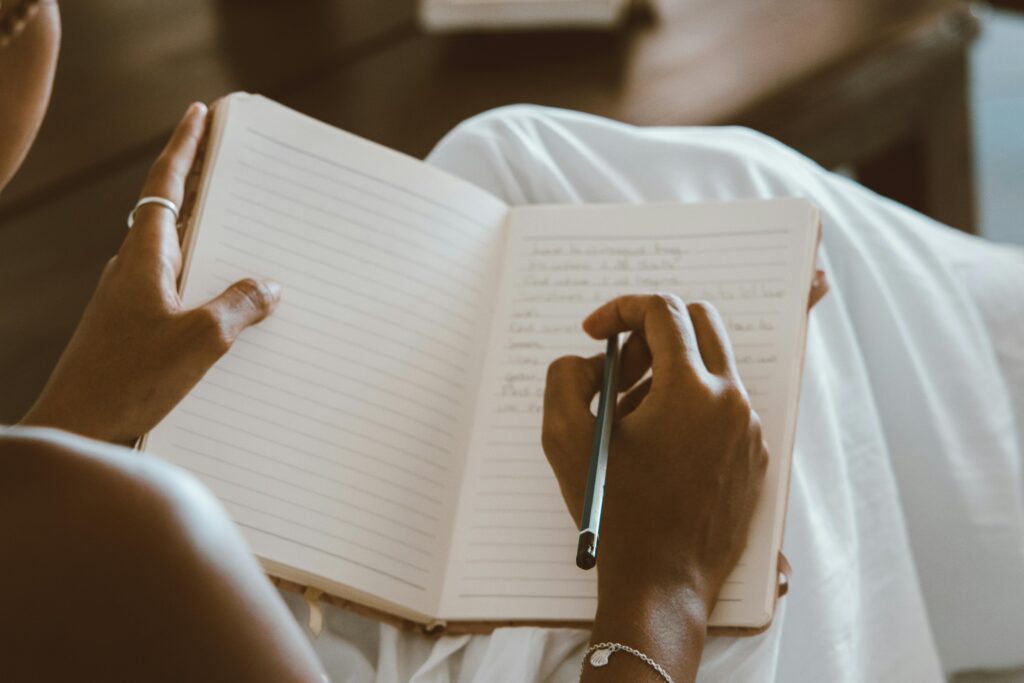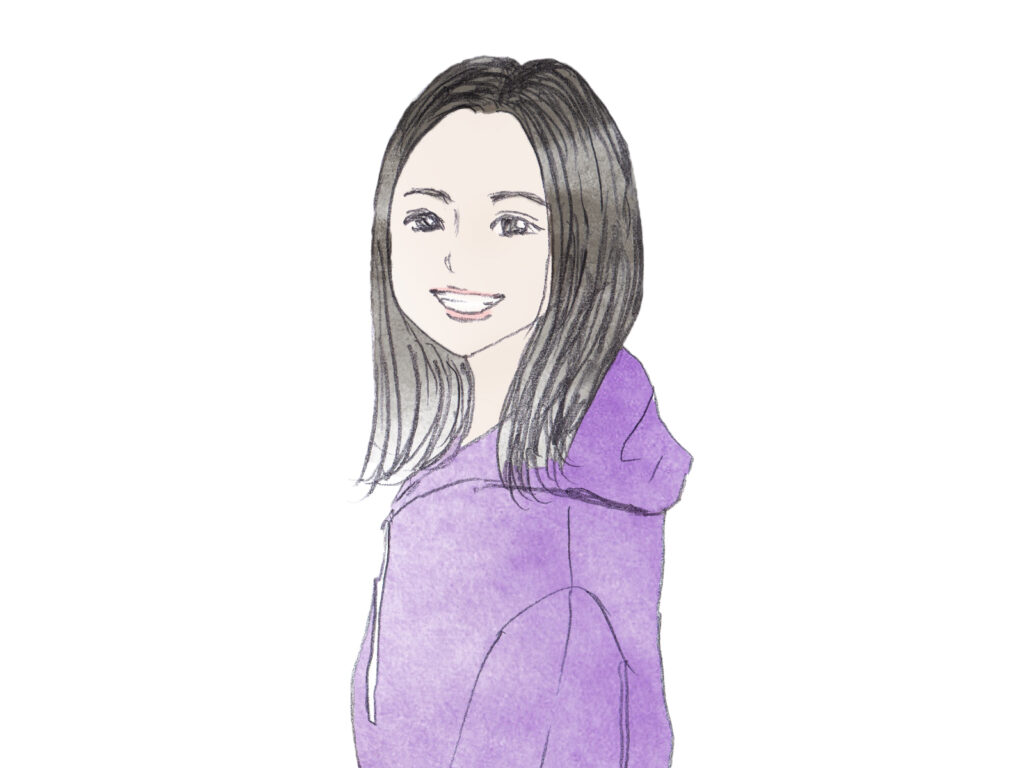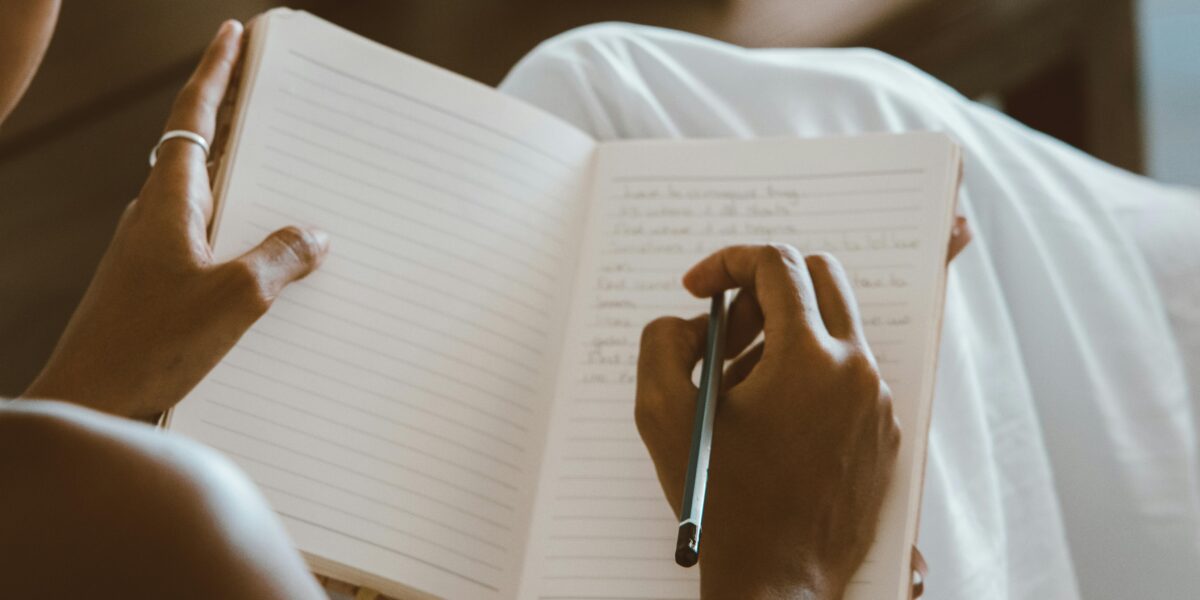
部下の成長を支援し、安心できる環境を作る
「わかってるつもり」で失敗した話
これは、わたしが40代前半の頃の話です。
新しいプロジェクトが始まって、わたしは後輩に
「このプロジェクトの責任者をお願いします」と声をかけました。
彼女の成長を応援するつもり、満天でした!
後輩は「はい、頑張ります」と答えました。
それから1ヶ月後。
プロジェクトの進捗確認をしたら、
ほとんど進んでいませんでした。
後輩は申し訳なさそうに「実は、どこから手をつけたらいいかわからなくて…」と打ち明けてくれました。
わたしは「任せた」と言っただけで、具体的な目標も方法も一緒に考えていなかったことを大いに反省しました。
これ、応援しているつもりで、実は何も支援できていなかったという典型的な失敗例です。
当時のわたしは、「言葉をかけること」と「実際に支援すること」の違いを、理解できていませんでした。
このことに気づいたとき、
わたしは自分の未熟さを痛感しました。
※今思えば、「任せる」という言葉の定義をお互いに共有していなかったことも問題だったと思います)
部下(相手)の成長を支援するとは?
信頼関係を築く2つ目のルールは、「相手の成長を支援する」ことです。
これは「頑張れ」と声をかけることではなく(それも大事な側面ですが)、
相手が実際に成長できるように、具体的なサポートをすること。
相手が成長すると、仕事の効率が上がります。
そして何より、相手自身が「自分は成長している」と実感できると、
仕事へのモチベーションが上がっていきます。
研修の現場で、参加者の方々から「部下をどう育てればいいのかわからない」という相談をよく受けます。わたしも、長年この問いと向き合ってきました。
答えは一つではないし、相手一人ひとりによって違います。
でも、共通して言えることがあります。
それは「具体的な支援」が必要だということです。
(抽象的な励ましだけでは、相手は動けないということですね)
目標設定と進捗の共有が大切
相手と一緒に目標を設定して、その進み具合を定期的に確認することが、成長支援の基本です。
先ほどの失敗の後、わたしは後輩と一緒に座って、プロジェクトを細かく分解しました。
「まず最初の1週間でここまで進めよう」
「2週間目にはこれを完成させよう」
「困ったことがあったら、すぐに相談してね」
このように、大きな目標を小さなステップに分けて、一つひとつ確認していくことで、後輩は「あ、これならできそう」と感じられるようになったんです。
目標は、できるだけ具体的に、そして「いつまでに、何を、どのレベルで」を明確にすることが大切です。
そして、途中で「今どんな感じ?」と声をかけて、一緒に進捗を確認する。
この小さな積み重ねが、相手に「ちゃんと見守ってくれている」という安心感を与えるというのがわたしの経験を通しての学びです。
研修の参加者の方が「目標を細かく分けることで、部下が自信を持って進められるようになりました」と話してくださったとき、わたしは「本当にその通りだな」と思いました。
(わたしも、そういう経験がありますから〜✨)
必要なスキルを教えるタイミング
相手に必要なスキルを身につけてもらうには、具体的な指導が必要です。
でも、これもタイミングが大事。
わたしはあわてんぼうなので(自覚しています😅)、
つい「これはこうやるんだよ!」と全部教えてしまいそうになります。
でも、それだと相手が自分で考える機会を奪ってしまう。
と、気づかされました。
研修で、参加者の方が「相手に考えさせることも大切ですよね」と発言されたとき、
それがわたしに向けられたフィードバックであることを認識できました。
わたしは「ああ、そうだった」とハッとしました。
自分が「教えたい」気持ちが先に立って、相手の「学ぶ機会」を奪っていたんだと。
おすすめは、必要な条件や形を伝えた上で「まず自分でやってみて、わからないところがあったら聞いて」というスタイル。
そして、定期的な勉強会やワークショップで、
チーム全体のスキルアップを図ることも効果的です。
わたしがサポートしているチームでは、月に一度「学び合いの時間」を作っています。
そこで、お互いに学んだことや「うまくいかなかったこと」
(※失敗談、という表現は使わないことにしました)を
共有しています。
そこから学べることが、わんさかあるわけです。
これが、チーム全体の成長につながっています。
心理的安全性って何だろう?
3つ目のルールは、「信頼を育む環境づくり」です。
最近よく聞く「心理的安全性」という言葉、
これがキーワードです。
心理的安全性とは、簡単に言えば「失敗(うまくいかないこと)しても大丈夫」「意見を言っても否定されない」と相手が感じられる環境のことです。
(提唱者:エイミー・エドモンドソン (Amy Edmondson) /Googleが提唱したことで有名になりましたね)
わたしの職場で以前、こんなことがありました。
会議で後輩が新しいアイデアを提案しようとしたとき、
わたしが早とちりで「それって、前にやって失敗したやつじゃない?」と
言ってしまったんです。
後輩は「あ、そうでしたっけ…」と黙ってしまいました。
その後、その後輩は会議で発言しなくなってしまいました。
わたしの一言が、心理的安全性を壊してしまったんです。
このとき、わたしは本当に反省しました。
「わたしの一言が、相手の可能性を閉ざしてしまったんだ」と。
会議後に、その後輩に謝りました。
「会議で、あなたのアイデアをちゃんと聞かずに否定してしまって、ごめんなさい。もう一度、そのアイデアを聞かせてもらえない?」
後輩からは「いえ、結構です」と言われてしまいました・・・・
本当に申し訳ないことをしたと思い、それ以後
・まずは最後まで聞く、
・遮らずに聴く、
・聞いた後に要約して確認する、
ことを意識してトライしています。
ところで、研修の中で、参加者の方々と「心理的安全性」について何度も議論を重ねてきました。その中で気づいたことは、心理的安全性は「誰かが作ってくれるもの」ではなく、「自分たちで作っていくもの」だということです。
ポジティブな姿勢で接する
相手に対してポジティブな姿勢で接することは、
信頼関係を築く上でとても大切です。
「ありがとう」「助かったよ」「よく頑張ったね」
という言葉は、相手にとって何よりのエネルギーになります。
わたしも意識的に、相手の良いところや頑張りを見つけて、
素直に伝えるようにしています。
もちろん、おだてるのではなく、
心から感謝や評価を伝えることが大事です。
相手はちゃんと本心かどうか見抜いてくれます。
(表面的な言葉は、むしろ逆効果になることもありますね)
研修で、ある管理職の方がこう話してくださいました。
「『ありがとう』を意識して言うようになってから、部下の表情が明るくなりました」
この言葉を聞いたとき、わたしは「やっぱり、小さな言葉が大きな変化を生むんだな」と実感しました。ただ、最近気づいたことがあります。
「ありがとう」の伝え方にも工夫が必要だということです。
「ありがとう」だけではなく、「何に対して」「どう助かったのか」を具体的に伝えることで、相手はより明確に自分の貢献を理解できるんだ、と気づきました。
例えば、
「ありがとう」ではなく、
「昨日の資料、すごくわかりやすくまとめてくれてありがとう。おかげでクライアントへの説明がスムーズにできたよ」
というように。
環境は一日では作れない
安心できる環境は、一日で作れるものではありません。
日々の小さな積み重ねが、少しずつ職場の雰囲気を変えていきます。
うまくいかないことがあっても「次はどうしたらいいか、一緒に考えよう」と言える関係。
意見が違っても「そういう考え方もあるね」と受け止められる雰囲気。
そんな環境を作ることが、信頼関係の土台になると思います。
これまでの仕事を通してわたしが学んだことは
「環境づくりには時間がかかる」ということです。
焦らず、一歩ずつ、進んでいきたいものです。
次回は、日常的なコミュニケーションと、
相手を尊重する態度について、具体的にお話しします。