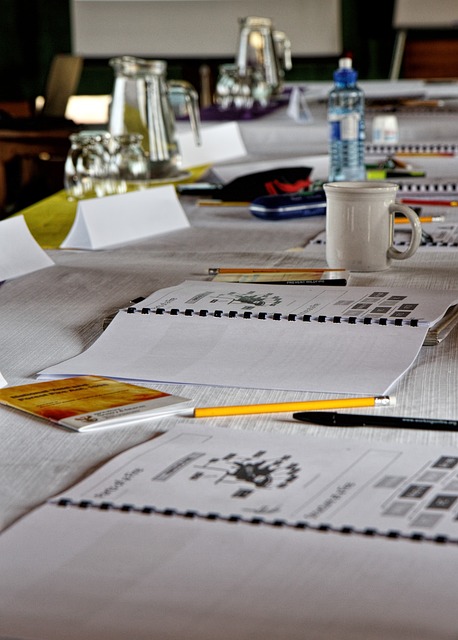〜部下指導で避けるべき5つの落とし穴〜
部下を指導する立場になると、どうしても「成果を出さなければ」「ちゃんと教えなければ」という気持ちが先に立ちがちです。
ところが、熱心に指導すればするほど、相手がプレッシャーを感じたり、やる気をなくしたりすることもあります。
“正しいやり方”を伝えればきっと部下は動いてくれるだろう、なんて、現実はそう単純ではありません。それは、指導は相手の状況や性格、置かれている環境の影響を大きく受けるからだと思います。
ここでは、部下指導でついやってしまいがちな落とし穴のひとつ「モチベーションを無視した指導」について取り上げます。
「そんなつもりじゃなかったのに、かえってやる気を削いでしまった」という失敗を防ぐためのヒントを、一緒に考えてみたいと思います。
落とし穴3:気持ちに配慮していない指導
部下指導でありがちな失敗のひとつが、「感情は本人の問題」と短絡的に処理をして指導の際にその側面をまったく考慮しないことです。
同じ業務を教えるときでも、成長意欲が高い部下には「新しいスキルが身につくよ」と伝えると目が輝くのに対し、目の前の仕事をこなすだけで精一杯な部下には「これができると負担が減るよ」と伝えた方が響きやすいことがあります。
「情熱がないなら仕方ない」と突き放すのは簡単ですが、そう見えるのは本当に本人の問題だけでしょうか。実際には、指導のタイミングや声のかけ方が、その人の感情に働きかけられていないだけの場合も少なくありません。
「正しい方法を教えること」だけに意識が向く結果として、相手は「また怒られるのかも」と萎縮し、余計に動けなくなってしまうこともあると思います。
タイプ別アプローチも大事な側面
指導は一律ではうまくいきません。
なぜなら、部下にも「できるようになりたい気持ちが強いタイプ」「周囲との調和を優先するタイプ」「失敗を極端に恐れるタイプ」など、性格や価値観の違いがあるからです。
こうした違いは、心理学や行動分析の世界では「行動傾向」として研究されてきました。たとえば、DISC理論では人の行動スタイルを
- D(主導型:挑戦を好む)
- I(社交型:人との関わりを重視する)
- S(安定型:安心感や調和を求める)
- C(慎重型:正確さやルールを重視する)
の4つに大きく分けています。
また、MBTIという性格分析では、外向・内向や意思決定の仕方の違いをベースにタイプを分け、同じ指導でも「どの言葉が響くか」が変わることが示されています。
つまり、性格や価値観の違いを知ることは、仕事への情熱や気持ちを引き出すヒントになるのです。
タイプ別アプローチ
ここでは、現場で使いやすいように、3つのタイプを簡単に整理してみます。
- 挑戦型(新しいことにワクワクするタイプ)
- 目標を大きめに設定し、「この経験はあなたの成長に繋がる」と伝えると響きやすいです。
- 細かすぎる指示は避け、自由度を残した方が成果を出しやすいでしょう。
- DISC理論では、D(主導型)に近い傾向です。自分の力を試す機会を与えるとパフォーマンスが上がります。
- 安定型(失敗を避けたい、慎重なタイプ)
- まずは成功体験を積ませることを優先し、小さなステップで進めるのが効果的です。
- 「ここまでできれば大丈夫」と安心感を与える声かけが響きます。
- DISC理論ではS(安定型)やC(慎重型)に近い傾向。ルールや段階的な進め方を示すことで動きやすくなります。
- 協調型(周囲との関係性を大事にするタイプ)
- 「この仕事はチーム全体にとって大切」と、他者への貢献を意識させると前向きになりやすいです。
- 個別の成果より、仲間との連携が活かせる役割を意識してもらうと力を発揮します。
- DISC理論のI(社交型)やS(安定型)に近い傾向があり、人間関係が動機づけになります。
もちろん、実際には複数のタイプが混ざっている人がほとんどですので、分類することが目的ではありません。
大切なのは「相手の視点から見て、どんな言葉が響くのか」を意識すること。
タイプを知ることは、そのヒントのひとつに過ぎないと思います。
部下指導は、正しい知識やスキルを伝えるだけでは十分ではありません。
相手の状態や価値観を無視してしまうと、せっかくの指導がプレッシャーや義務感に変わり、かえってやる気を奪ってしまうこともあります。「この人は今、どんな気持ちでいるだろう?」と想像し、タイプに合わせた言葉がけや進め方を意識することで、指導はもっと前向きなものに変わっていきます。
心理学の理論は難しそうに思えるかもしれませんが、相手のタイプを知ると指導がしやすくなるのではないでしょうか。
指導は「こちらが教えるもの」ではなく、「相手が受け取るもの」。
だからこそ、相手の心に届く形を探ることが大切なのだと思います。