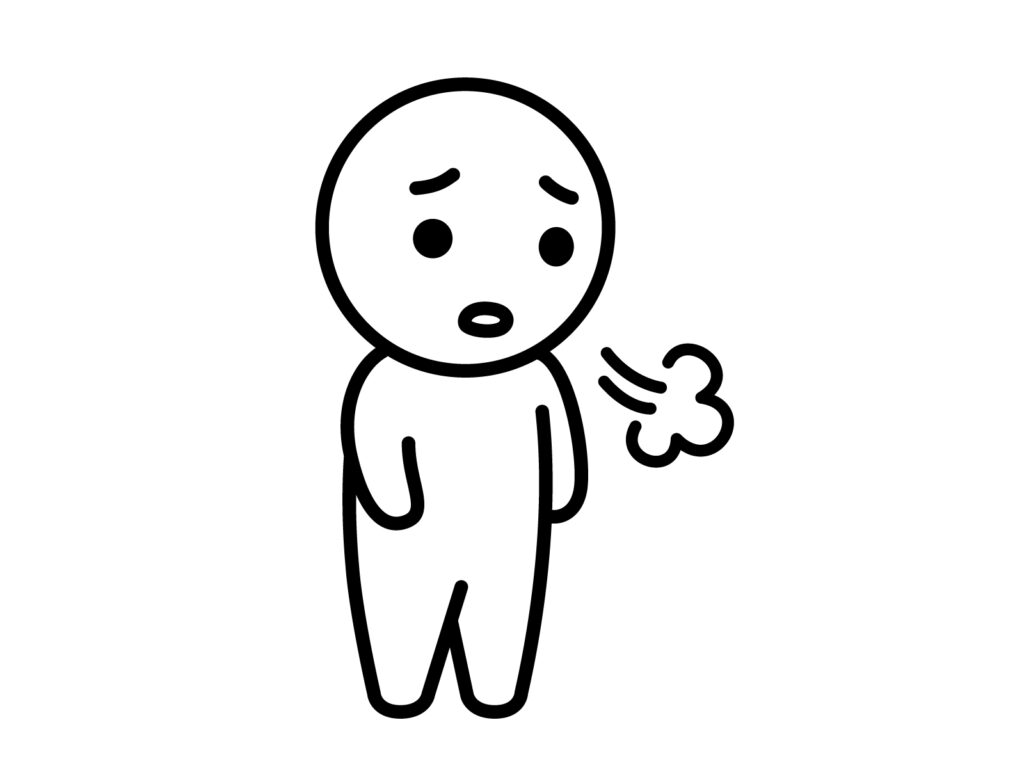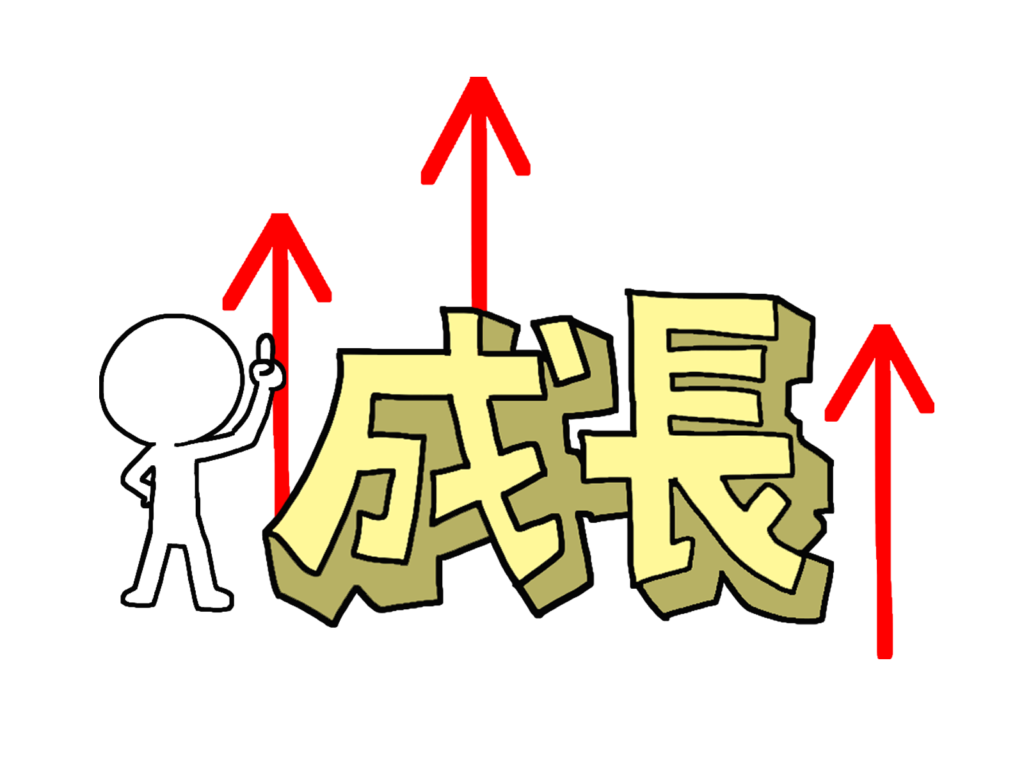自分の中に生まれた感情に対処できない
ビジネスの現場で、「あの人、もっとこうすればいいのに」と思うことはありませんか?
部下の報告が要領を得ない、同僚のプレゼンに改善点が目立つ…。そんなとき、私たちはつい「もどかしさ」や「イライラ」、あるいは「優越感」といった感情を抱いてしまうことがあります。
私自身も、研修講師として参加者の“できていない部分”ばかりに目が向き、「正しいやり方」を示したくなることが何度もありました。でも、そんな自分の内側に目を向けたとき、大切な気づきがありました。
「相手の課題が見える時、そこには自分の課題がある」

もう20年ほど前の話ですが
人間関係トレーナーからこう言われました。
「相手の課題が見えた時、そこにはあなた自身の課題があるよ」と。そして、様々な現場を経験し、自分を見つめ直す中で、この言葉の奥深さを実感するようになっていきました。
たとえば、部長が部下の意見を聞いていないと感じるとき、実は私自身も、他者の意見に耳を傾ける余裕を失っていたり。「あの人はもっと自己主張すべきだ」と思ったとき、自分の中にも「本当は言いたいことを抑えている自分」がいたり。
このように、自分が他者に対して何を感じるかは、自分自身の課題を映す鏡でもあるのです。
その前提に「感情」のプロセスがある

しかし、こうした“自己への気づき”に辿り着く前に、私たちは感情を経験します。
例えば、ある人が発言した内容に、強い違和感を覚えて「それは違う」と思わず言い返したくなるような気持ちが込み上げ、冷静に考える余裕がなくなるケース。
脳科学的に見ても、これは自然な反応です。人の脳は、まず感情(扁桃体)で反応し、後から理性(前頭前野)が働く構造になっています。つまり、「相手の課題」に反応した瞬間、まずは自分の中に感情が湧き上がり、思考より先に“感情の波”が押し寄せます。
ある営業部長の方のお話を思い出します。「部下が報告書を期限までに出してこないこと」にイライラしていました。しかし、自分のその感情にしっかり向き合ってみたとき、実は「自分が、経営陣への報告が出せなくなることに意識が向いていた。部下を育てたりマネジメントする以前の問題だったように思う」と気づいたそうです。
感情をきっかけに、自分自身を深く見つめ直すことで、新たな行動が生まれます。
感情に対処する方法:私の実践例から

では、相手の言動によって湧き上がった「もやもや」や「イライラ」に、どう向き合えばよいのでしょうか。私自身が日々の現場で取り組み、効果を感じている方法をいくつかご紹介します。
- 感情にラベルを貼る
「私は今、怒っている」「焦っている」と、まずは素直に認識することが第一歩です。
私は、研修中に感情が湧いたとき、小さなメモに「怒り」「不安」などと書いておくようにしています。文字にすることで、自分の内面を客観視しやすくなります。
- 深呼吸と「間」をつくる
感情が強く出そうな時は、すぐに反応せず、意識的に深呼吸し、「少し考えてから答えますね」と時間を置くようにしています。
あるクライアント企業では、会議中に「5分間だけ考える時間」を設けるだけで、感情的な衝突が激減したという例もあります。
- 自分を三人称で語る
「私は」ではなく、「平澤は今、怒っているな」と語ることで、感情との距離が少し取れます。
この小さな視点の変化が、自分を冷静に保つコツになります。
相手の課題に気づけるということは、見方を変えれば「自分が変われるチャンス」に出会っているということでもあります。
だからこそ、まずはその前段階にある「感情」に気づき、適切に対処する力を身につけることが、リーダーとしての成長の鍵になるのではないでしょうか。
他者を導く立場にある皆さんにこそ、自分の中に生まれた感情と丁寧に向き合い、その感情を手がかりに自己成長のヒントを見つけていただければと思います。
それが、結果的にチームの成熟や信頼の土台を築くことにもつながるのですから。