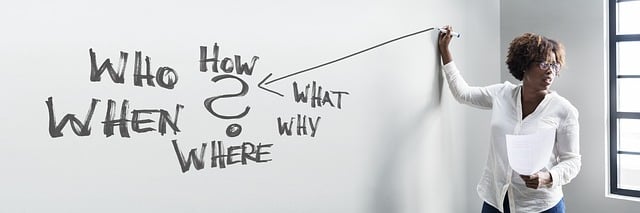先日、あるトップ企業の記者会見をYouTubeで見ていました。
※実際のYouTube動画の内容を編集し、動画を特定でいないようにしました。ご了承の上でお読みください。
質問に立った記者が「御社の新事業は前CEO時代の失敗を繰り返していると言われていますが、どのようにお考えですか?」と質問したのです。これは典型的な「前提が証明されていない質問」でした。
現CEOは冷静に「その質問にはいくつかの未証明の前提があります。まず、前CEO時代に『失敗』と断定できる事業があったのか、次に現在の事業がそれと同じ構造を持つのか、さらに『繰り返している』という評価が社会的に共有されているのか、という点です。これらの前提が成立していない以上、質問自体が成り立ちません。ただし、新事業の現状と展望については、別途お答えできます」と返答しました。
論理的なやりとりについて、考えさせられる場面です。
例えば、わたしの経験から挙げられる例としては「なぜうちの部署は常に遅れているのですか?」といった前提付きの質問に、管理職が思わず弁明してしまうケースです。
問に説明はいらない

1、問に説明jはいらない
2、問いと説明をこじつけない
3、説明をこじつけることで、問に対する答えを誘導することになる
論理的な対話では、まず「問いが適切か」を確認することが大切です。
例えば部門会議で「なぜこの施策は失敗したのか」と質問されたとき、その施策が本当に「失敗」と言えるのかを問い直すことは建設的な議論の第一歩です。
私がある企業の管理職研修で経験した例を挙げましょう。
マネージャーが「部下が常に言い訳ばかりする」と問題提起しました。
いくつか質問をさせていただき、「常に」という言葉の妥当性や「言い訳」の定義を掘り下げていくと、実は「特定の状況で説明が長くなる傾向がある」という具体的な課題に絞られました。
問題の本質が明確になったことで、具体的な改善策を考えられるようになったのです。
その罠にハマらないこと
答えられないことを無理に答えてはいけない。
それは無理に質問に対する答えを作ることになる。
質問者も、そのことを踏まえた上で公的に質問するものとしての責任を果たすことが求められるでしょう。
以前、人事部の方と打ち合わせをした時「これまでヒヤリハットの研修をして来たけれど、効果がなかった」の発言を聞きました。この発言には「効果がなかった」という未検証の前提が含まれていました。発言者にとっては効果がないように見えたのですが、現場でのヒヤリハットの件数は前年比で20%以上減少しており、その内容を見ると大きな成果が出たと診断できるものでした。
仕事でやり取りを通して大切だと思うことに一つに、
・誠実に答えようとする姿勢を保ちながらも
・論理的な整理を行うこと
です。
「その質問にお答えする前に、これまでの研修の効果測定データを確認させてください。もし効果が不十分だった領域があれば、その原因と改善点について議論できます」といった応答をすると、議論の焦点が定まり内容も深掘りできるのではないでしょうか。
重要なのは、無理に答えを作り出さないことだと思います。
答えられない質問に誠実に「現時点では答えられない」と伝えることも、信頼構築につながるのではないでしょうか。もちろん、今後の対応も示す必要がありますが。
私が関わったある経営陣は「わからないことをわからないと言える文化」を大切にしており、それが組織全体の透明性と論理性を育てていきました。
論理的に物事を考えられることは、強みである。
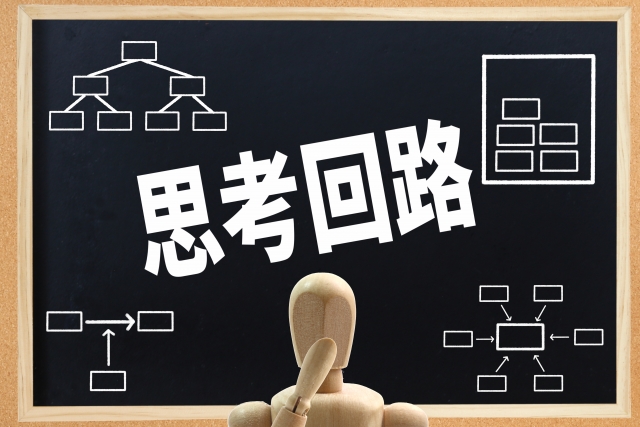
論理的思考は、感情や先入観に流されずに本質を見極める力だと思います。
これはリーダーシップの根幹をなすスキルのようにも思えます。
特に不確実性の高い現代ビジネスでは欠かせません。
ある経営者の方が「社員がもっと論理的に考えられるようになれば」とお話をしていらっしゃいました。よくお聞きしてみると、「論理性の欠如」というよりも、「質問と回答のミスマッチ」のように思えました。質問の前提を確認せずに回答してしまうパターンが繰り返されていた印象です。(あくまでも印象。その場にいたわけではないので)。
質問の論理構造を分析する
「質問の論理構造を分析する」というワークショップを実施するのも面白いのではないでしょうか。
参加者は自分の質問や回答をふりかえって、前提を明確にする訓練を重ねていく。
そして数ヶ月後・・・、会議の質が向上し、問題解決のスピードが格段に上がった、なんていうケースも十分にあり得ると思います!
論理的思考力を高める研修は、単なる知識習得ではなく、日常のコミュニケーションに織り込まれるべきものではないでしょうか。もちろん、完璧に一人一人が、と言っているのではなく、やり取りを通してみんなで論理的に議論を深めていくのです。
その一歩として、まずは自分の発する質問や回答の前提を意識することから始めてみる、というのもありだと思います!そして部下や同僚との対話で「この質問の前提は何だろう?」と考える着眼点を用意する。こうして、そこに意識が向いて考える習慣がつくと、職場の論理性と生産性は徐々に、であったとしても、より高まっていく、と思うのです。

当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて
無料相談会を開催しています。
ヒューレット・パッカード社の創業者が残した「人の成長なくして企業の成長はない」というメッセージは、その後リーマンショック等を経て事実上各社で証明され続けている実態があります。こうしたことからも、企業では社員を育成するための様々な研修を企画されていることと思います。
当研究所では、研修のご導入をご検討の企業担当者の方に向けて企業様ごとの個別無料のオンライン相談会を開催させていただいております。お気軽にお問合せ・お申し込みください。
そのほか、自社の研修を新たに導入することに関するご相談をオンラインでお受けしています。
・現状ではどういった研修を導入すると良いのか
・研修はどの頻度で実施すると良いのか
・フォローアップはどのように進めると効果があがりやすいのか
・階層ごとにどういった教育が必要なのか
・自社の教育体系施策を作成したいが、作り方がわからないし現実的かがわからない
など、従業員育成に関するあらゆるご相談を無料でお受けしております。
ご希望の方は、以下のお申し込みフォームからお申し込みください。
追ってご連絡をいたします。
ぜひ、無料個別相談をご利用ください。
組織こうどう研究所